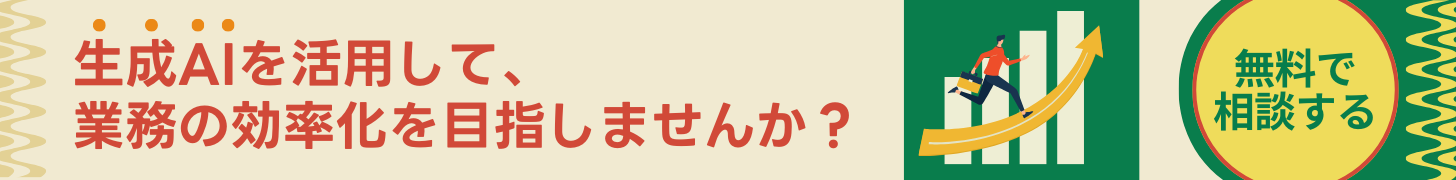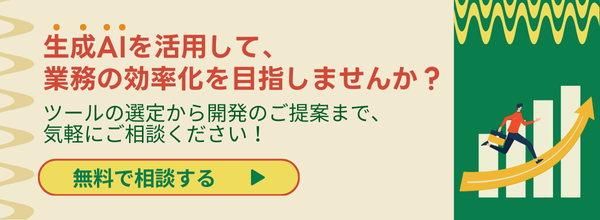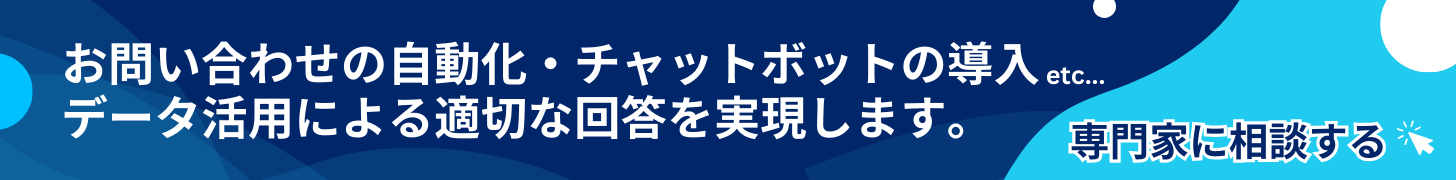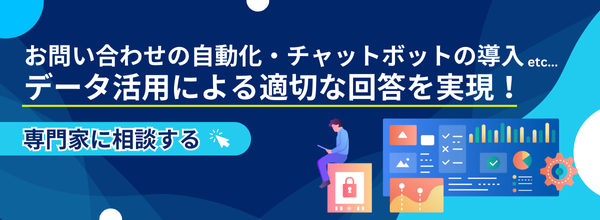【社内データの有効活用】オンプレ×RAGで実現する業務効率化!メリットや導入方法を詳しく解説
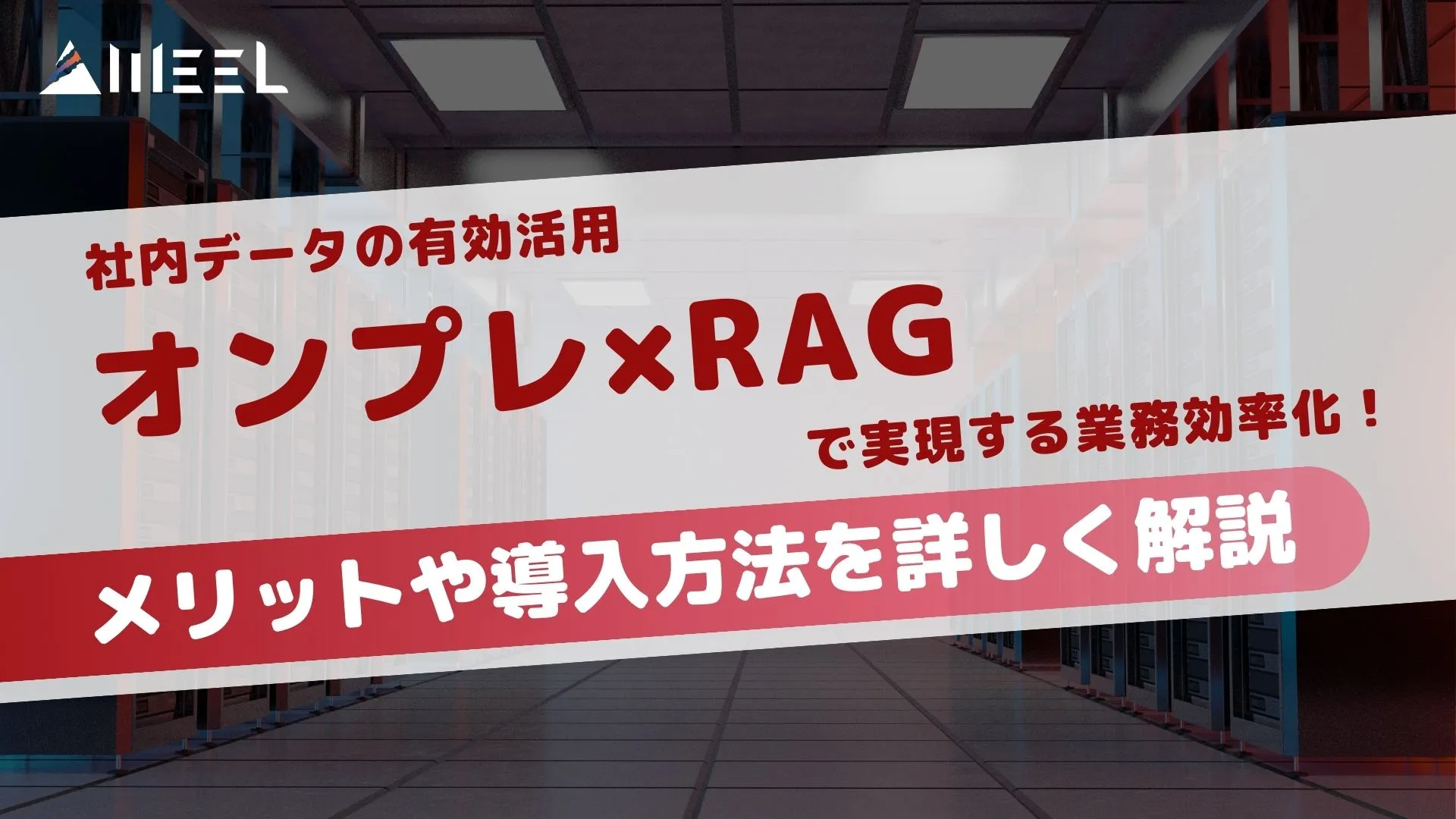
- オンプレミス環境にRAGを組み合わせることで、セキュリティ・処理速度・コスト面での優位性を保ちながら、高精度な応答生成が可能となる。
- RAGはファインチューニング不要で導入でき、最新情報や社内ナレッジの活用にも適した柔軟性の高い技術である。
- 実店舗の接客や社内ノウハウの共有など、クラウド利用が制限される業務においても、オンプレ×RAGは高い実用性を発揮する。
生成AIの活用が進む中、「外部にデータを出せない」「クラウドの利用に制限がある」といった理由から、オンプレミス環境での導入を模索する企業が増えています。
中でも注目されているのが、社内データを活用して精度の高い応答を実現できるRAG(Retrieval-Augmented Generation)との組み合わせです。
本記事では、RAGの基礎からファインチューニングとの違い、オンプレで導入する際の手順やメリット、おすすめの日本語対応モデル、実際の活用シーンまでを分かりやすく解説します。
「オンプレ×RAG」による業務効率化と情報活用の最前線をご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください!
\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/
オンプレ×RAGの可能性
オンプレミスとは、システムの稼働に不可欠なハードウェアとソフトウェアを自社で保有する運用形態のことを指します。社外のハードウェアをインターネット経由で借用する新しい運用形態「クラウド」と区別する呼称で、現在では時代遅れの技術のように扱われています。
しかし近年、クラウド一辺倒だったシステム構成に変化が生まれ、「オンプレ回帰」の流れが注目を集め始めました。特に、生成AIを活用した業務効率化においては、RAG(Retrieval-Augmented Generation)との相性が非常に良好です。
RAGは社内に蓄積された独自データと組み合わせることで、汎用LLMでは得られない高度な応答生成が可能となります。オンプレミス環境での運用は、セキュリティやコスト、処理速度の面でも優位性を発揮し、AI導入の選択肢として再評価されつつあります。
そもそもRAGとは?
RAG(Retrieval-Augmented Generation)とは、情報検索と自然言語生成を組み合わせて生成AIの回答精度を向上させる技術です。
通常の大規模言語モデル(LLM)は事前学習された知識をもとに回答を生成しますが、RAGでは外部のデータベースや文書群から関連情報を検索(Retrieve)し、それを参照しながら文章を生成(Generate)します。こうすることで、モデルの知識カットオフ以降の最新情報や、企業固有のナレッジにも柔軟に対応可能となるメリットがあるのです。
たとえば、社内マニュアルやFAQ、製品仕様書などを取り込むことで、企業情報を学習したより精度の高い業務支援が可能になります。ファインチューニング不要で柔軟性が高く、さまざまな業務に適応できるのがRAGの強みです。
なお、RAGの開発事例について詳しく知りたい方は、下記の記事を併せてご確認ください。
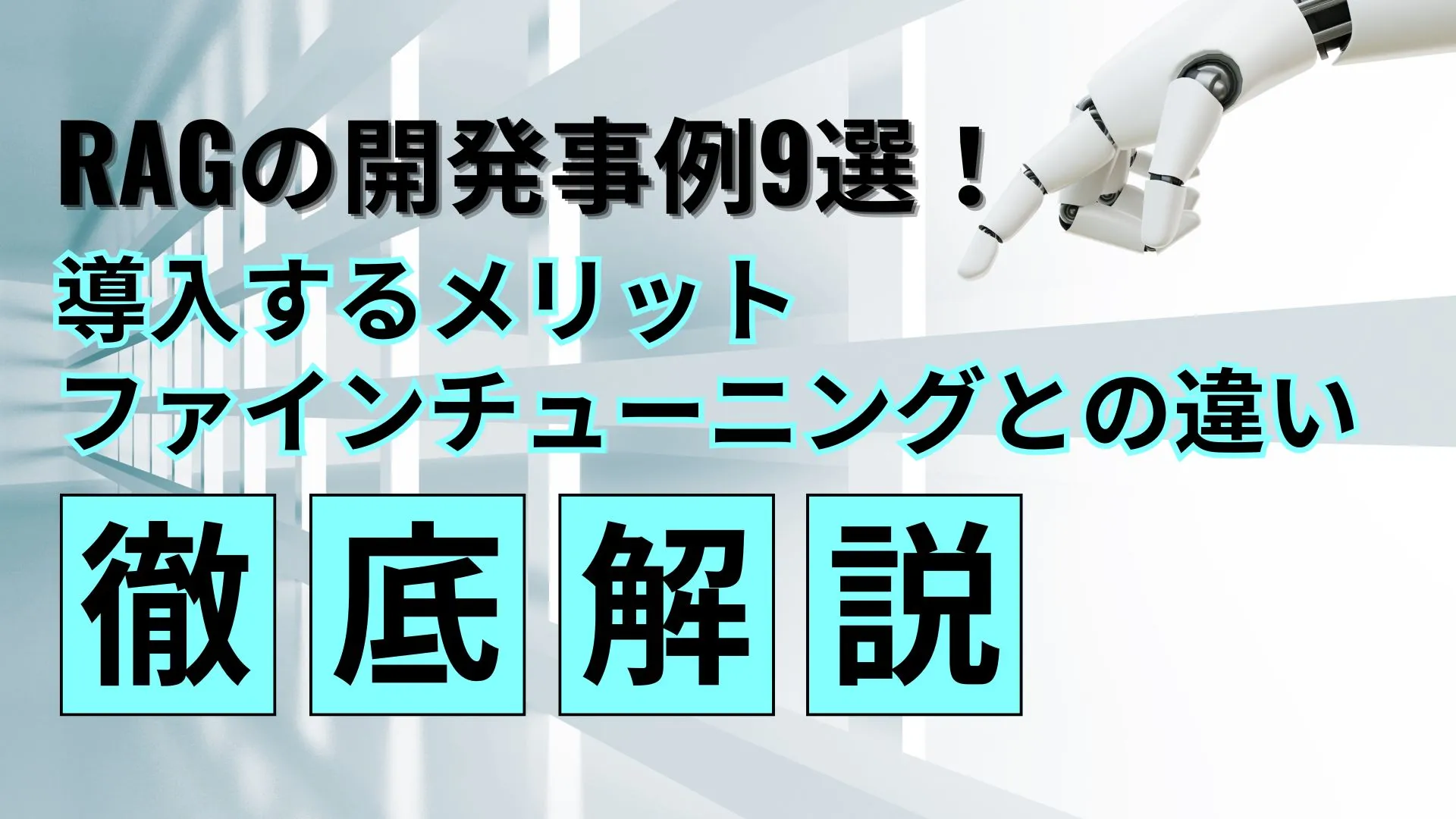
RAGとファインチューニングの違い
RAGとファインチューニングは、どちらも生成AIを特定業務に最適化する方法ですが、その仕組みや使い方には明確な違いがあります。
- ファインチューニング
既存の大規模言語モデルに対して追加学習を行い、モデル自体のパラメータを更新します。
→ 高度な精度が得られる一方で、学習コストや開発期間がかかり、柔軟性に欠ける点も。 - RAG(検索拡張生成)
モデルは外部データベースから関連情報をリアルタイムで取得し、それを参照して応答を生成します。
→ モデルの再学習が不要で、ナレッジの更新も容易。導入・運用のハードルが低いのが特徴です。
このように、更新頻度の高い情報や社内データを活用したい場合には、RAGのほうが効率的かつ柔軟に対応できます。
オンプレミスでRAGを活用するメリット
RAGは、クラウド環境だけでなくオンプレミス環境でも高い効果を発揮します。特に、セキュリティや業務要件の厳しい業界においては、オンプレ運用による安心感と柔軟性が大きなメリットとなるでしょう。
以下で、オンプレミス環境でRAGを活用する4つのメリットをご紹介します。
データ等を社内で完結させられる
オンプレミス環境でRAGを導入する最大のメリットの1つが、社内データを完全に内部で処理できる点です。
たとえば、医療や金融、保険、製造業など機密性の高い情報を扱う業種では、外部クラウドにデータを預けることに対する懸念が根強くあります。しかしオンプレミスであれば、データの出入りを最小限に抑え、厳格な情報管理ポリシーのもとで生成AIを活用できます。
加えて、インターネット接続が不要なクローズドな環境でも運用可能なため、ガバナンスや内部統制の観点からも安心です。
処理速度に優れる
オンプレミスでは、クラウドに比べてデータの送受信にかかる通信遅延がなく、応答速度の高速化が図れます。特に、大量のベクトル検索や生成タスクを連続して実行する業務では、この処理速度の違いが体感レベルで業務効率に影響します。
また、自社環境に最適化されたハードウェア構成を組むことで、パフォーマンスをさらに向上させることも可能です。リアルタイム性が求められる接客業務や分析業務などにおいて、オンプレ×RAGの組み合わせは大きなアドバンテージとなるでしょう。
運用コストが抑えられる
オンプレミスは初期導入にこそ一定の設備投資が必要ですが、稼働後のランニングコストを大きく抑えられるのも大きなメリットです。
クラウドのような従量課金は発生せず、実際の運用にかかる費用は電力代やハードの保守費用程度です。また、自社サーバーであれば夜間や休日など稼働の空き時間を活用し、大量のアイデア生成やバッチ処理を走らせるといった柔軟な運用も可能になります。
長期的に使い込むほど、コストメリットは大きくなっていくのです。
拡張性にも優れる
オンプレミスでRAGを構築する最大の魅力とも言えるのが、システム全体の自由度の高さです。
特定のクラウドプラットフォームに縛られることなく、利用するLLMや埋め込みモデル、ベクトルデータベースなどを柔軟に入れ替えられます。たとえば、UI部分にはSaaSを活用しながら、裏側のモデル処理は自社で最適な構成にカスタマイズする、といったハイブリッドな運用も可能です。
将来的なモデルの更新や用途拡大にも対応しやすく、AIシステムを中長期で育てていきたい企業にとって理想的な環境と言えますね。
オンプレ環境へのRAG導入の流れ
オンプレミスでRAGを導入するには、段階的かつ綿密な準備が不可欠です。要件整理から環境設計、実装、運用まで、各フェーズを確実に進めることが成功の鍵となります。
それぞれのフェーズについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
要件定義
RAG導入プロジェクトの最初のステップは「要件定義」です。
まず、現状の業務課題や改善したいプロセスを明確化し、それらがRAGの導入によって本当に解決できるのかを慎重に検討する必要があります。たとえば「社内ナレッジの検索性を高めたい」「特定の問い合わせ対応を自動化したい」といった目的を具体的に洗い出し、それに対するRAGの有効性を評価します。
また、RAGとファインチューニングのどちらが適しているか、あるいは併用すべきかといった技術部分における選定もこの段階で行いましょう。
環境設計
要件定義をもとに、RAGを実行するためのハードウェア・ソフトウェア環境を設計します。
特に重要なのは、適切なGPUリソースの確保です。生成処理やベクトル検索には高い計算能力が求められるため、NVIDIA製の高性能GPUと、それに対応したサーバー構成が一般的です。また、OSやミドルウェア、開発言語、フレームワーク(LangChain、LlamaIndexなど)も選定対象となります。
オンプレ環境での運用を想定した場合、冷却・電源・ネットワーク構成などインフラ面の考慮も欠かせません。安定稼働とスケーラビリティの両立が求められます。
RAGシステムの設計
RAGの中核となるシステム設計では、複数の要素を組み合わせて最適な構成を構築します。
まず、検索対象となるドキュメント群をベクトル化するための「埋め込みモデル」を選定し、それを保存・検索する「ベクトルデータベース」(FAISS、Weaviateなど)を設計します。さらに、生成部分を担うLLM(大規模言語モデル)を決定し、必要に応じて軽微なプロンプト設計やチューニングを加えることで、精度と応答性の調整が可能です。
ユーザーとのインターフェース設計も重要で、UXを意識した入出力形式や利用シーンに応じた拡張性も考慮する必要があります。
運用・保守
RAGシステムを安定的に運用するためには、継続的な保守体制の構築が欠かせません。
たとえば、社内ドキュメントの追加・更新に応じて、埋め込みデータやインデックスの再構築を定期的に行う必要があります。また、LLMやベクトルDB、周辺ライブラリのアップデート対応や、障害時の復旧手順の整備も重要です。
ログ監視や性能モニタリングの仕組みを導入することで、トラブルの早期検知と対応も可能になります。運用負荷を軽減するには、ジョブの自動化や管理ツールの導入も効果的です。
オンプレ×RAGで使える日本語LLM
オンプレミスでRAGを構築する際、日本語に特化した小型LLMの選定は重要なポイントです。ここでは、特に注目すべき国産モデルを3つご紹介します。
tsuzumi

「tsuzumi」はNTTとRIKENが共同開発した、軽量でありながら世界トップレベルの日本語処理性能を持つ大規模言語モデルです。約70億パラメータとコンパクトながらも、ビジネス用途に適した高精度な応答が可能です。ライセンスが明確で商用利用も視野に入れやすく、オンプレミス環境への導入も比較的容易です。RAGとの連携によって、高度な日本語応答システムを構築できます。
cotomi

「cotomi」は、NECが独自開発した日本語特化の軽量LLMで、軽量でありながら実用的な応答性能を備えています。特に、日本語表現の自然さや口語・文語の柔軟な取り扱いに強みがあり、RAGと組み合わせることでより的確な情報提示が可能になります。MITライセンスで公開されており、オンプレでの利用も技術的・法的に扱いやすい点が魅力です。
TinySwallow-1.5B

「TinySwallow-1.5B」は、日本のAI企業「Sakana AI」が開発した推論性能と省リソース性のバランスに優れた日本語特化の小型LLMです。
15億パラメータながら、自然な対話と高度な文章理解を両立しており、RAGとの組み合わせにも適しています。特にGPUリソースが限られるオンプレ環境において、実用性と安定性の両面から高評価を得ています。商用利用も可能なライセンス体系で、実務導入に向いた選択肢といえるでしょう。
なお、SLMについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご確認ください。
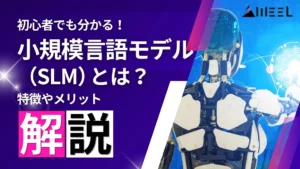
オンプレ×RAGの活用シーン
オンプレミスでRAGを導入することで、さまざまな業務現場での効率化や自動化を実現するのも夢ではありません。以下に代表的な活用例を紹介します。
実店舗での顧客対応
接客スタッフがその場で商品情報や在庫状況、使い方などを即答することが求められる実店舗では、オンプレ環境でRAGを導入することで非常に大きな効果が期待できます。
たとえば、社内に蓄積されたFAQやマニュアル、商品データベースを取り込むことで、これらを基にした高度な応答が可能になり、スタッフの接客品質を大きく向上させられます。クラウド接続が制限された店舗やセキュアなネットワーク内での運用が必要な場合でも、オンプレミスであれば安定した運用が実現できます。
実店舗で「オンプレ×RAG」の活用を進めることで、顧客満足度の向上と業務効率化の両立が可能です。
社内ノウハウのリサーチ
企業内には、ベテラン社員の経験や過去の資料、議事録など、形式知化されていない貴重なナレッジが大量に眠っていることも多いでしょう。
ここに「オンプレ×RAG」を活用すれば、これらの社内情報をベクトル化し、自然言語で柔軟に検索・応答できるようになります。特定の部署に偏っていた知識も全社で横断的に活用可能になり、業務の属人化を防ぐ効果も期待できます。
また、社外へのデータ送信を伴わないため、機密情報を含むナレッジの活用にも適しており、人材育成や業務継承の支援ツールとしても非常に有効です。
なお、RAGチャットボットで業務効率を上げる方法について詳しく知りたい方は、下記の記事を併せてご確認ください。
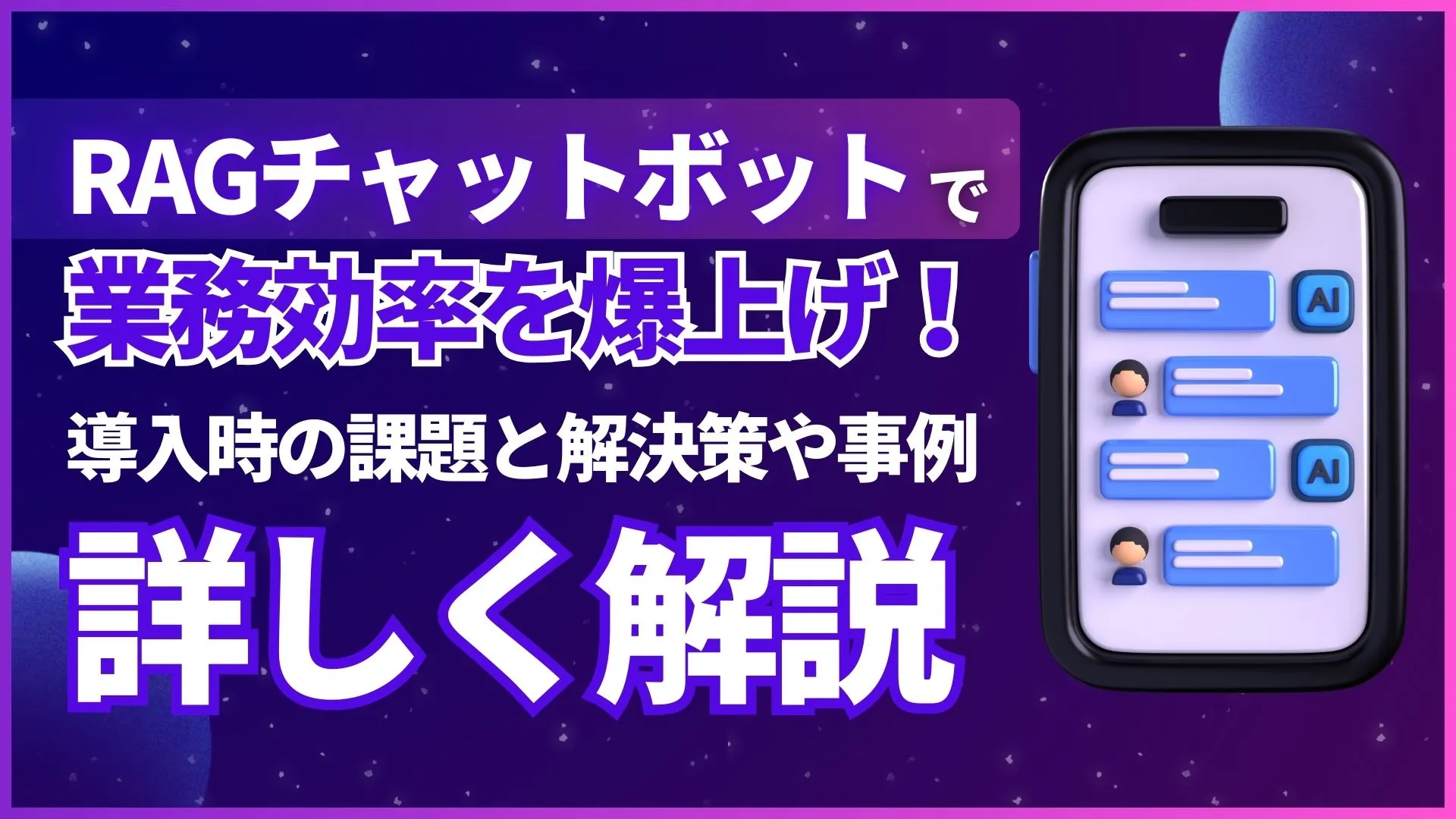
まとめ
RAGの柔軟性とオンプレミス環境の制御性を組み合わせることで、企業はより安全かつ効果的に生成AIを活用できるようになります。特に、高セキュリティ・高精度が求められる業務において、その真価を発揮するでしょう。
オンプレ×RAGで実現できることを簡単にまとめました。
- 社内ナレッジの有効活用と属人化の解消
- セキュアかつ高速な情報検索・応答環境
- 自社仕様に応じたシステムの柔軟な拡張
- 長期的視点でのコスト最適化と内製化推進
生成AI導入を次のフェーズへ進めたい企業にとって、オンプレミス環境でRAGを導入することは非常に有用な手段となるはずです。ぜひ活用を検討してみてください!

最後に
いかがだったでしょうか?
オンプレ環境でのRAG導入は、セキュリティと効率性を両立できる有力な選択肢です。最適な導入方法を検討してみませんか?
株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!
開発実績として、
・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント
・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット
・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト
・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール
・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用
・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント
などの開発実績がございます。
生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。
➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。
まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。
➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。
セミナー内容や料金については、ご相談ください。
また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。

【監修者】田村 洋樹
株式会社WEELの代表取締役として、AI導入支援や生成AIを活用した業務改革を中心に、アドバイザリー・プロジェクトマネジメント・講演活動など多面的な立場で企業を支援している。
これまでに累計25社以上のAIアドバイザリーを担当し、企業向けセミナーや大学講義を通じて、のべ10,000人を超える受講者に対して実践的な知見を提供。上場企業や国立大学などでの登壇実績も多く、日本HP主催「HP Future Ready AI Conference 2024」や、インテル主催「Intel Connection Japan 2024」など、業界を代表するカンファレンスにも登壇している。