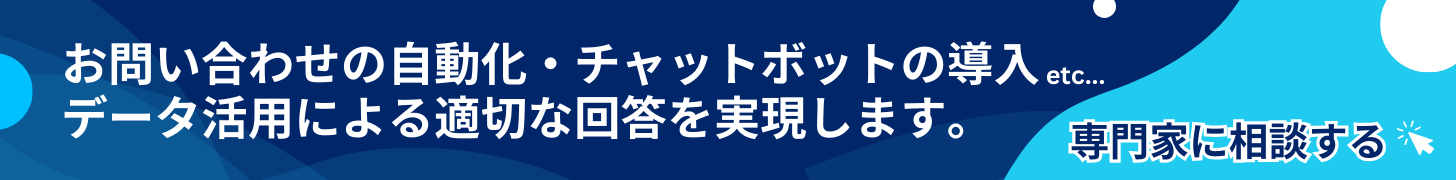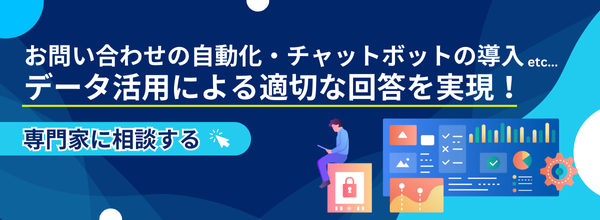ECサイト運営における生成AI活用術5選!導入メリットやプロンプトを紹介!

- EC展開を強化したい方
- グローバル展開を考える企業の越境EC担当者
- 需要予測に関心がある方
- AIを活用した在庫管理・サプライチェーンを最適化したい方
生成AIの進化が目覚ましい今、EC事業においてもAI活用が広がっています。顧客対応の効率化から需要予測まで、生成AIはさまざまな場面で活躍しています。
本記事では、EC事業における生成AIの普及状況や具体的な活用事例、導入時の注意点までを詳しく解説します。AIの力を借りてEC事業を成長させたい方必読の内容です。
\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/
ECサイト運営における生成AIの普及率

EC事業での生成AI活用は、着実に広がりを見せています。調査によると、EC事業者の約3割がすでに生成AIを導入済みか導入を検討中とのこと。この数字は今後さらに増加すると予想されるでしょう。※1
生成AIの導入が進む背景には、競争激化するEC市場での差別化や業務効率化のニーズがあります。大手ECサイトだけでなく、中小規模の事業者も積極的に生成AIの導入を進めている状況です。
業界別に見ると、ファッションや美容関連のEC事業で特に導入が進んでいます。商品の特徴や使い方を詳しく説明する必要がある分野では、生成AIによるコンテンツ作成の効率化が大きなメリットとなっているようです。
なお、中小企業の生成AI活用について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。
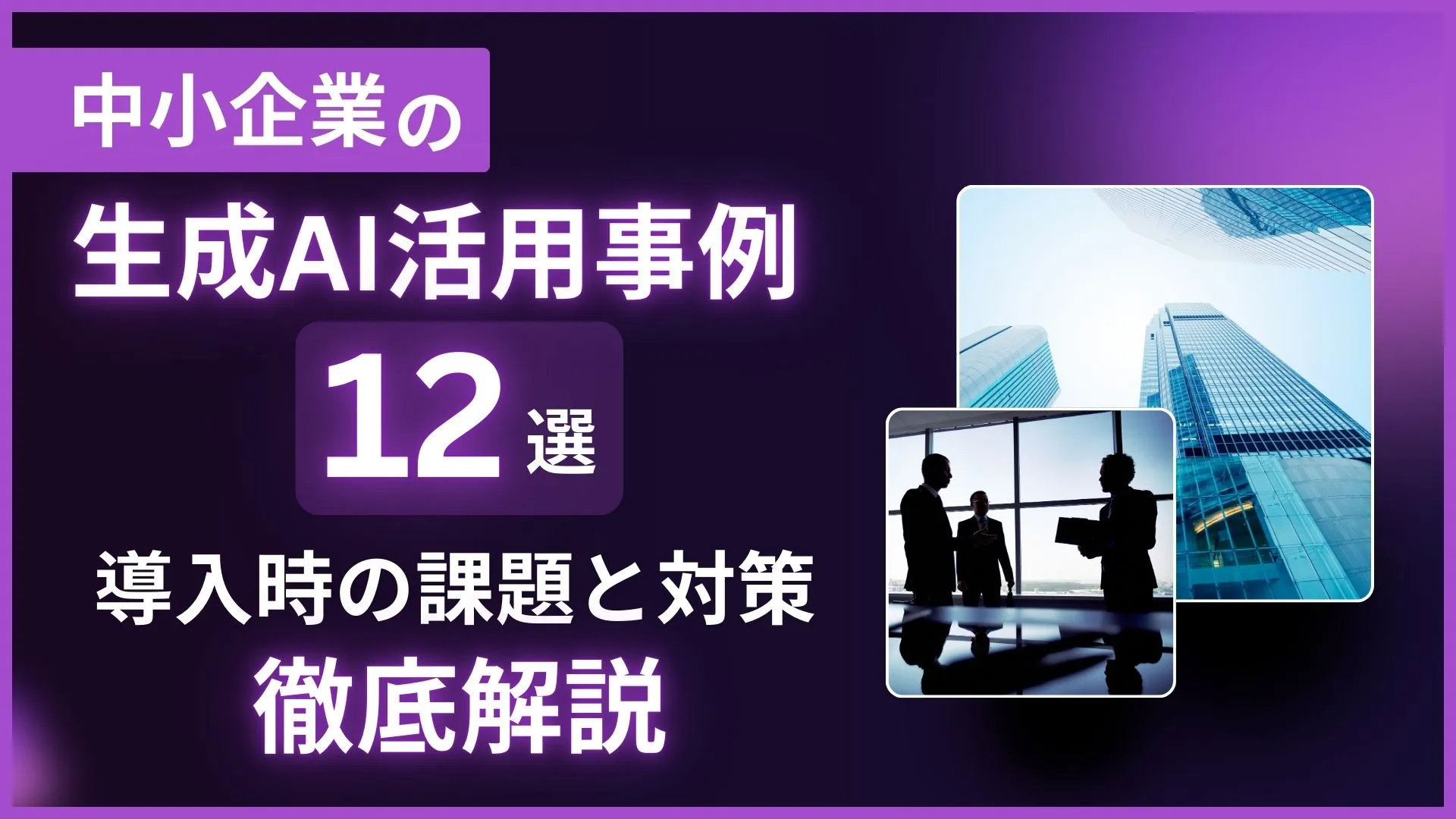
ECサイト運営で生成AIを活用するメリット
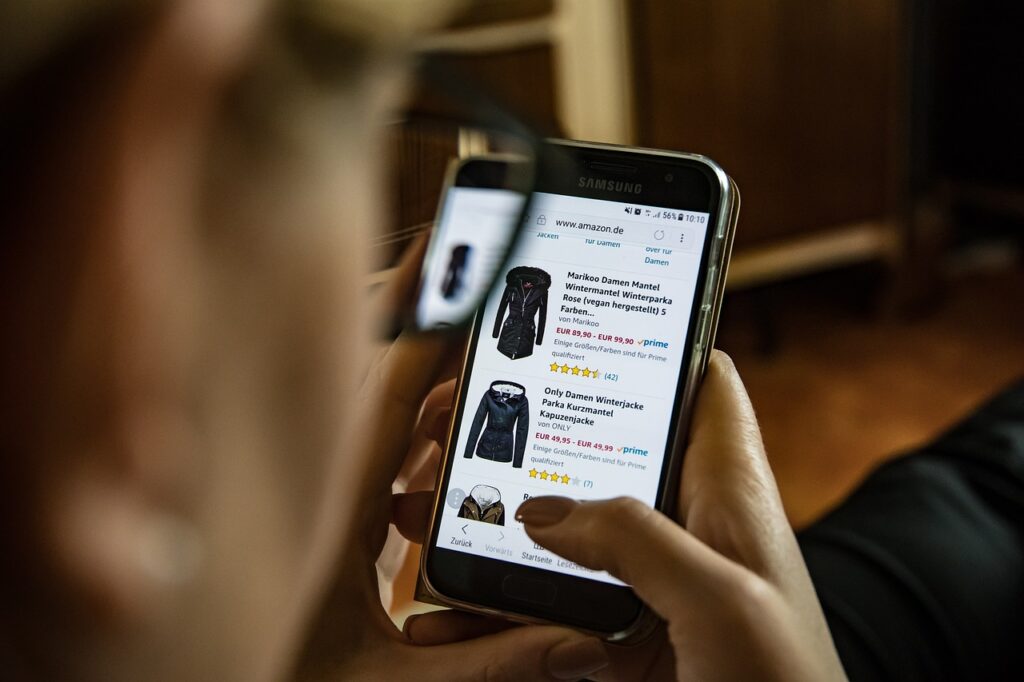
生成AIの活用はEC事業に多くのメリットがあります。EC事業者にとって、生成AIの導入は業務効率化や顧客満足度向上につながる可能性を秘めていますが、具体的にどのような場面で役立つのでしょうか。
ここでは、主な活用メリットを5つ紹介します。
チャットボットで顧客対応を効率化できる
チャットボットサービスの導入により、企業の顧客対応が進化しています。24時間365日、深夜や休日でもお客様の問い合わせにすぐに対応可能。システムは日々の対応から学習を重ね、よくある質問への回答の質が向上します。その結果、待ち時間の短縮とコスト削減を実現可能です。
年末年始などの混雑期でも、チャットボットは複数のお客様に同時対応が可能なため、長時間待ちの解消につながります。さらに、やり取りの内容を自動で記録・分析できる機能により、継続的なサービス品質の向上にもつながっています。

コンテンツの作成ができる(SEO対策も可能)
EC事業では、商品説明やブログ記事など、魅力的なコンテンツが欠かせません。生成AIを使うことで、基本情報を入力するだけで簡単に商品説明文が作成可能。人間が書いた文章をさらに読みやすく整えることもでき、制作時間の大幅な短縮が期待できます。
生成AIは、商品の特徴や利点を的確にとらえ、興味を引く表現で文章を作り上げます。SEOに配慮した文章も得意としており、検索順位の向上にもつながるでしょう。季節やターゲット層に応じて文章のトーンを調整したり、商品のストーリー性を引き出したりと、幅広いニーズに対応できる点も魅力です。
パーソナライズされた商品レコメンドで購買率向上につながる
生成AIは、顧客の購買履歴や行動データを分析して、個々のニーズに合った商品を提案します。これまでの「この商品を見た人は~」といったシステムよりも、より精度の高いレコメンドが可能です。一人ひとりの好みやタイミングに合わせた提案は、購買率の向上にもつながります。
AIは、購入履歴や閲覧データ、検索キーワードなどを分析し、さらに季節や流行、年齢層なども考慮して商品を提案してくれます。リアルタイムで学習を続けるため、提案の精度も向上。その結果、顧客が求める商品を見つけやすくなり、結果として売上の増加が期待できるでしょう。
AIショッピングアシスタントで顧客満足度が向上する
AIショッピングアシスタントを導入すれば、顧客が探している商品をAIチャットボットがいち早く提案してくれます。顧客は膨大な量の商品から、自分に最適な一品を見つけられるため、顧客満足度が向上するのは間違いありません。
例えば、パソコンを自作しようとしている顧客がいれば、パソコンを自作するのに必要なPCケースやメモリなどのパーツを提案してくれます。
AmazonのAWSなどがAIショッピングアシスタントを提供しているので、興味がある方はチェックしてみてください。※7
データ分析による需要予測ができる
生成AIは、過去の販売データはもちろん、天気予報や経済の動き、SNSでの話題まで、さまざまな情報を組み合わせて、より正確な予測が可能です。正確な予測ができれば、在庫の管理やセールの計画が、より細やかに立てられるようになります。
例えば、大きなスポーツイベントが近づくと関連商品の売れ行きが伸びたり、天気の変化で特定の商品の需要が急増したりといった変化も、事前に読み取れるようになるでしょう。さらに、業界全体の動向や競合他社の状況なども考慮に入れることで、より広い視野での予測が可能になります。
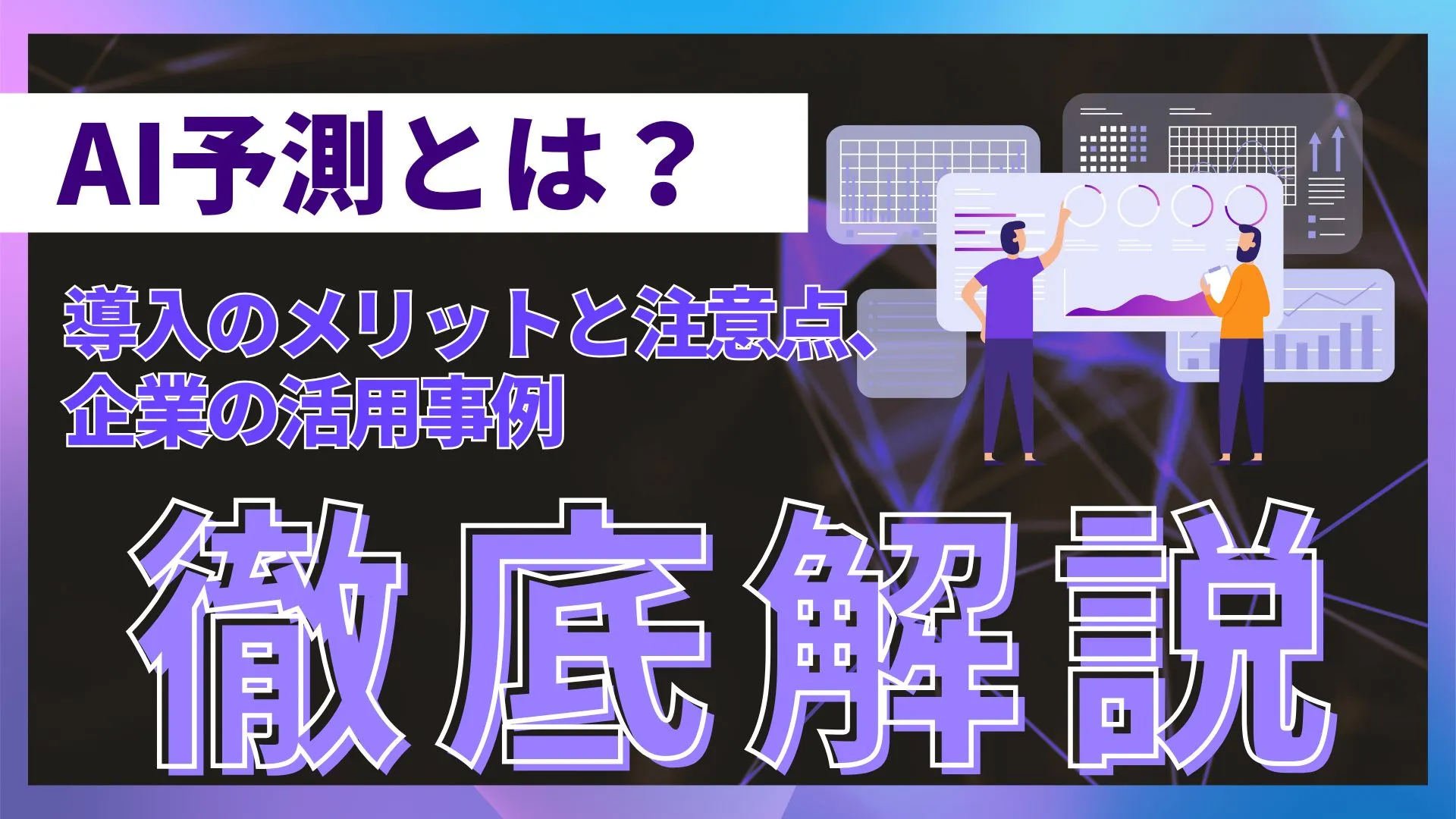
多言語での対応が可能
EC事業で海外展開を考えるとき、最も大きな壁となるのが言語の問題です。最近では、最新の翻訳技術を活用することで、この課題を乗り越える企業が増えてきました。商品の説明から顧客対応まで、複数の言語でスムーズにサービスを提供できるようになっています。
AI活用で特に心強いのは、単純な機械翻訳とは違って、それぞれの国の文化や慣習に合わせた自然な表現が可能です。日々の対応を通じて翻訳の質も向上し、現地のお客様が読んでも違和感がないような内容に仕上げられるでしょう。
ECサイト運営で今すぐできる生成AI活用術5選!【プロンプト付き】
注文システムの導入や改変、AIチャットボットの導入などは多くの時間と手間がかかりますが、文章作成のタスクであれば今すぐ生成AIで効率化できます。
ここでは、ECサイト運営で今すぐできる生成AI活用術をプロンプト付きで紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
商品説明文の作成
ChatGPTなどのツールを使えば、商品の特徴を簡潔かつ魅力的に言語化でき、作業時間も大幅に削減できます。特に商品数が多いショップでは、大幅な業務効率化につながるはずです。
生成AIを活用する際は、誰に向けた商品なのか、どんな特徴やメリットがあるのかを具体的に整理して伝えるのがコツです。トーンや文字数も明確に指示すると、理想に近い文章が生成されます。
生成後は必ず事実確認と微調整を行いましょう。
プロンプト例
#命令
あなたは優秀なECサイトのコピーライターです。
以下の商品情報をもとに、購買意欲を高める商品説明文を作成してください。
【商品情報】
・商品名:
・価格:
・特徴:
・ターゲット層:
・セールスポイント:
#条件
・文字数:200文字程度
・トーン:親しみやすく丁寧な「です・ます調」
・強調したい点:商品の特徴と使うことで得られるメリット
・ブランドの雰囲気に合った表現を心がける商品名・キャッチコピーのアイデア出し
生成AIは短時間で複数のネーミングやキャッチコピーを提案してくれるため、アイデア出しのスピードが格段に上がります。新商品の打ち出しや既存商品のイメージ刷新にも効果的です。
生成精度を高めるには、商品の魅力や特徴、ターゲット層、使用シーンなどを具体的に伝えることが重要です。対話を繰り返すことで、より良い案が浮かび上がります。
プロンプト例
#命令
あなたは優秀なECサイトのコピーライターです。
以下の商品情報をもとに、魅力的な商品名とキャッチコピーをそれぞれ10案ずつ考えてください。
【商品情報】
・商品カテゴリ:天然素材のハンドメイドトートバッグ
・特徴:軽量、環境にやさしい素材、日本製
・ターゲット層:30代女性、ナチュラル志向
・用途:普段使いやピクニック、買い物など
#条件
・商品名:短く、響きが柔らかく覚えやすいもの
・キャッチコピー:20〜30文字程度
・トーン:ナチュラルでおしゃれな印象
・ブランドイメージ:「丁寧な暮らし」を大切にするメルマガ用の文章作成
生成AIを使えば、キャンペーン告知や新商品紹介など、メルマガに必要な文章を短時間で作成できます。読者に合わせたトーンや内容で複数パターン出せるため、A/Bテストにも活用しやすいのが特徴です。
作成の際は、誰に向けて何を伝えたいのかを明確にし、配信の目的(クリック誘導・購入促進・ブランディングなど)を意識して指示を出すのがポイントです。導入文から訴求ポイント、締めの一言まで構成の流れも伝えると、より効果的な文章になります。
プロンプト例
#命令
あなたは優秀なメルマガライターです。
以下の情報をもとに、読み手の興味を引くメルマガ本文を作成してください。
【配信目的】新作アイテムの発売告知
【ターゲット層】20〜30代の女性
【商品情報】ナチュラル素材のワンピース、着心地の良さが特徴
【キャンペーン情報】発売記念で全品10%オフ(8/10まで)
#条件
・文字数:500文字以内
・トーン:親しみやすく前向きな「です・ます調」
・構成:導入→商品紹介→キャンペーン訴求→行動喚起
・ブランドの雰囲気に合った柔らかい表現を心がけるキャンペーン企画の考案
生成AIを活用すれば、季節やイベント、販売状況に合わせたキャンペーンアイデアを多数提案してもらえます。思考の幅を広げたいときや、スピーディーに案を出したい場面で便利です。
実際に活用する際は、キャンペーンの目的(売上アップ、在庫処分、新規顧客の獲得など)やターゲット層、扱う商品ジャンルなどを具体的に伝えましょう。必要に応じて実施時期や予算の条件も加えておくと現実的な企画案が出やすくなります。
プロンプト例
#命令
あなたは優秀なマーケティング担当者です。
以下の条件をもとに、ECサイト向けのキャンペーン企画を5案提案してください。
【目的】新規顧客の獲得
【対象商品】夏用ファッションアイテム(ワンピース・サンダル・帽子)
【ターゲット層】20〜30代女性
【開催時期】8月中旬〜9月上旬
#条件
・1案ごとにキャンペーン名、内容、実施期間、想定される効果を明記
・実現可能な範囲の内容にすること
・トーン:提案資料に使えるよう簡潔かつ明確に問い合わせ対応用のテンプレート作成
生成AIを使えば、よくある問い合わせへの返信文や、クレーム対応・遅延のお詫びなど、場面ごとの対応文をスムーズに作成できます。対応のばらつきを防ぎながら、丁寧な印象を与える文章を効率よく用意できるのがメリットです。
活用する際は、状況やお客様の感情に応じた対応ができるよう、具体的な背景や伝えたい内容を明確に伝えるのがポイントです。フォーマルさの度合いや、謝罪・説明・お礼など含めるべき要素も事前に指示しておくと、実用性の高い文面が生成されます。
プロンプト例
#命令
あなたは丁寧なカスタマーサポート担当です。
以下の状況に応じた、お客様対応メールの文面を作成してください。
【状況】注文商品の発送が遅延しており、1週間後の発送になる見込み
【お客様の状況】すでに発送予定日を過ぎており、不安を感じている可能性がある
#条件
・文字数:300文字以内
・トーン:丁寧かつ安心感を与える「です・ます調」
・構成:お詫び→理由説明→対応内容→今後の案内
・必要に応じて、お詫びの気持ちが伝わる一文を添えることなお、ChatGPTの文章作成で使えるプロンプトを詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

ECサイト運営で生成AIを導入する手順
ECサイト運営に限らず、生成AIを闇雲に導入するのはおすすめしません。具体的なゴールを決めずに生成AIを導入するのが目的になってしまうと、業務が効率化されないまま導入費用が無駄になってしまいます。
以下では、ECサイト運営で生成AIを導入する具体的な手順を紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。
ステップ1.活用目的と業務フローを整理する
生成AIを導入するには、まず何のために使うかをはっきりさせることが重要です。商品説明文作成や問い合わせ対応など、具体的な業務を絞り込みましょう。
そのうえで現在の業務フローを見直し、AIを組み込む最適なポイントを洗い出します。目的と流れが明確になることで、導入後の効果も高まり、無駄な工数が増えません。
初めから多くのことを成し遂げようとせず、優先度の高い業務から着手するのがおすすめです。
ステップ2. 適切な生成AIツールを選定する
生成AIツールは多数ありますが、目的や予算に合ったものを選ぶことが成功の鍵です。ChatGPTやClaudeなど、得意分野や使いやすさが異なるツールを比較検討しましょう。
無料プランやトライアルを活用して、操作感や生成品質を実際に試すのもおすすめです。また、API連携やセキュリティ面も確認して、自社環境に適したツールを選定してください。
ステップ3. 必要な情報をテンプレート化する
生成AIに渡す情報は、あらかじめ整理してテンプレート化しておくと効率的です。商品スペックやターゲット層、使用シーンなど、項目ごとにまとめましょう。
統一フォーマットがあると、毎回の入力作業が簡単になるだけでなく、生成される文章の質も安定します。また、情報の抜けや誤りを防ぐ効果もあるため、信頼性の高いアウトプットにつながります。
ステップ4. プロトタイプを作成して試験的に運用する
まずは小規模でプロトタイプを作り、実際の業務で試験的に使ってみましょう。この段階でプロンプトの精度や運用フローの課題を洗い出すことが重要です。
現場のフィードバックを受けて改善を重ねることで、運用開始後のトラブルを減らし、スムーズな導入が可能になります。無理に完璧を目指さず、段階的に進めることが成功のコツです。
ステップ5. 本格運用と改善を繰り返す
プロトタイプでの検証を経て、生成AIを業務に正式に組み込みます。運用開始後も、生成される文章の品質や業務効率を定期的にチェックしましょう。ユーザーやスタッフからのフィードバックをもとに、プロンプトやテンプレートの調整を続けることが重要です。こうしたPDCAサイクルを回すことで、効果を最大化し、安定した運用が実現します。
ECサイト運営での生成AIの活用事例

生成AIの活用は、すでに多くのEC事業者で始まっています。各社の事例から、生成AIがEC事業にもたらす具体的な効果や可能性が見えてくるでしょう。
ここでは、新しい取り組みを行っている企業の事例を紹介します。
資生堂
資生堂の公式オンラインショップ「ワタシプラス」は、LINE公式アカウントを活用して売上を大幅に伸ばしています。※2
2022年11月末から導入したチャットボット機能により、LINE経由の売上が前年比20~30%増を記録。さらに、チャットボット機能の拡充後は売上が10%以上伸びました。
ワタシプラスは、LINE公式アカウントを「第2のECサイト」と位置づけ、既存顧客とのエンゲージメント強化に力を入れています。ユーザーはLINE上で商品検索から購入までをシームレスに完結できるため、利便性が高く、リピート購入につながりやすい環境を実現。LINE公式アカウントは、メールマガジンや各種広告と比較して、最も売上に直結するコミュニケーション手段となっています。
ZOZO
ZOZOは、生成AIを活用した「アイテムレビューパトロール」という独自ツールを開発し、2024年4月から運用を開始しました。※3
このツールは、ZOZOTOWNユーザーが投稿するアイテムレビューに対し、ガイドライン違反を自動で検出。大規模言語モデルを使用しており、検出されたレビューは担当者が目視で確認します。
導入から4か月間で、ガイドライン違反チェックの業務時間を67.7%削減し、チェック件数を68.5%削減したとのこと。以前は担当者が全てのレビューを目視でチェックしていましたが、このツールにより違反の可能性が高いレビューのみをチェックすればよくなり、生産性の向上につながりました。
メルカリ
メルカリは、2024年9月10日より「AI出品サポート」機能の提供を開始しました。※4
この機能により、ユーザーは写真を撮ってカテゴリーを選ぶだけで商品情報の入力が完了し、最短3タップで出品が可能。AIが商品の写真から自動的にタイトル、商品説明、商品状態、販売価格などの情報を生成します。
これまで出品時の商品情報入力に負担を感じていたユーザーや、出品作業の面倒さから出品を手間に感じていたユーザーにとって、大きなサポートとなっています。自動入力された内容は、出品者が必要に応じて編集することも可能です。
ORBIS株式会社
ORBIS株式会社は、自社運営サイトのオルビス公式オンラインショップにおいて、「awoo AI」で作成した独自のハッシュタグを活用しています。※5
「SNSバズり中」や「冬におすすめ」などのタグを生成して運用することで、サイト利用者が新しい商品と効率的に出会える環境作りに成功しました。
具体的な成果として、CVR改善率が4.6倍になったとのことです。
株式会社ビックカメラ
株式会社ビックカメラは、自社運営サイトのビックカメラ・ドットコムにて、AI技術を活用したSaaSのクラウド型商品マスタ「Lazuli PDP」を導入しています。※6
「Lazuli PDP」は自動で商品情報を集めて整備・連携できるため、担当者が商品登録にかかる負担を軽減しつつ、商品情報の拡充や品揃えの充実化を実現していく予定とのことです。
商品登録に時間を割いている担当者の方は、品揃えを効率的に増やしていくためにも、ぜひこの取り組みを真似してみてください。
ECサイト運営で生成AIを導入する際の注意点
生成AIの導入には大きなメリットがありますが、導入の際に気をつけたい点もあります。これらの注意点をしっかり理解し、適切な対策を取ることで、生成AIの効果を最大限に引き出せるでしょう。
ここでは、EC事業者が生成AIを導入する際に気をつけるべきポイントを解説します。
導入コストがかかる
AIシステムの導入には思いのほか手間がかかります。高性能なサーバーやネットワークの整備など、システム面での初期投資は避けられません。さらに、意外と見落としがちなのが、AIの学習データを集めて整理する作業です。これにも予想以上の時間と費用が必要になってきます。
特に中小規模でECを運営されている企業にとって、この初期投資は大きなハードルになるでしょう。そのような場合は、クラウドベースのAIサービスを利用するなど、初期の負担を抑えながら自社のペースで少しずつAI導入を進めるのも一つの方法です。
継続的なアップデートやメンテナンスが必要
AIを活用するには、導入後の地道な取り組みが欠かせません。例えば、より正確な結果を出すために、定期的に新しいデータを使って学習させたり、AIが予期せぬ動きをしたときにすぐに対処できる体制を整えたりする必要があります。
AIのアップデートやメンテナンスには専門的な知識が必要ですが、社内にそうした人材がいない場合は外部の専門家に依頼することになります。その際は、それなりの費用は覚悟しなければなりません。
AIの導入を検討されている企業の皆様は、こうした導入後のコストや体制づくりについても、事前に検討されることをお勧めします。
機密情報の漏洩につながる可能性がある
多くの企業でAIの導入が進んでいますが、「情報の安全性」を忘れてはいけません。AIを活用している中で、お客様の個人情報や社内の機密情報を扱うことがあるでしょう。そのため、しっかりとした情報管理の仕組みが欠かせません。
具体的にどんなリスクがあるのかと言うと、AIシステムへの不正アクセスや、学習用データからの情報漏洩などが考えられます。こうしたリスクから大切な情報を守るには、データの匿名化や暗号化といった対策を重ねる必要があります。
なお、生成AIのリスク対策について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

ECサイト運営の生成AI活用が当たり前の時代に!
EC事業におけるAIの活用は、今や欠かせない存在となっています。顧客対応の効率化やパーソナライズされたサービスの提供など、生成AIはEC事業に多くの可能性をもたらします。
ただAIを導入すれば成功するわけではありません。しっかりとした計画を立てて、導入を進めることが成功の秘訣です。具体的には、以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。
- 自社が抱える課題や必要としているものを明確にし、それに合った方法で活用する
- いきなり全面導入するのではなく、段階的に取り入れ、費用対効果を慎重に見極める
- AIが使う学習データを定期的に更新し、システムをメンテナンスし続ける
- 顧客情報を守るためのセキュリティ対策を徹底する
- AIの特性を活かしつつ、人間の判断と組み合わせて運用する
確かに生成AIは強力なサポートになりますが、「これさえあれば全てうまくいく」と考えていてはいけません。人間ならではの発想や判断力と上手く組み合わせることで、その力を発揮します。自社の強みを活かしながら、新しい技術を取り入れることで、ビジネスを次のステージへと進めることができるでしょう。

最後に
いかがだったでしょうか?
EC事業の競争が激化する中、生成AIの導入で顧客対応の効率化、パーソナライズレコメンド、需要予測が可能に。業務コストを抑えつつ売上向上を実現しませんか?貴社に最適なAI活用戦略をご提案します。
株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!
開発実績として、
・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント
・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット
・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト
・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール
・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用
・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント
などの開発実績がございます。
生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。
➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。
まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。
➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。
セミナー内容や料金については、ご相談ください。
また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。

【監修者】田村 洋樹
株式会社WEELの代表取締役として、AI導入支援や生成AIを活用した業務改革を中心に、アドバイザリー・プロジェクトマネジメント・講演活動など多面的な立場で企業を支援している。
これまでに累計25社以上のAIアドバイザリーを担当し、企業向けセミナーや大学講義を通じて、のべ10,000人を超える受講者に対して実践的な知見を提供。上場企業や国立大学などでの登壇実績も多く、日本HP主催「HP Future Ready AI Conference 2024」や、インテル主催「Intel Connection Japan 2024」など、業界を代表するカンファレンスにも登壇している。