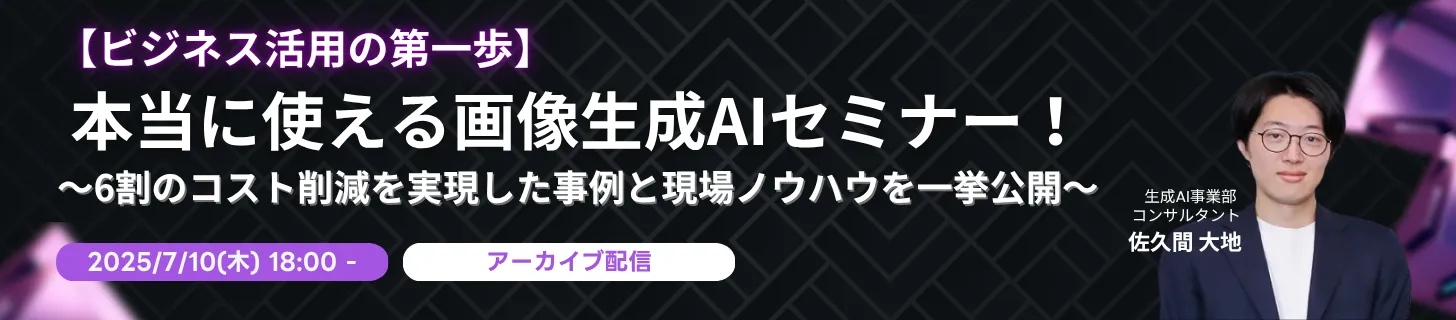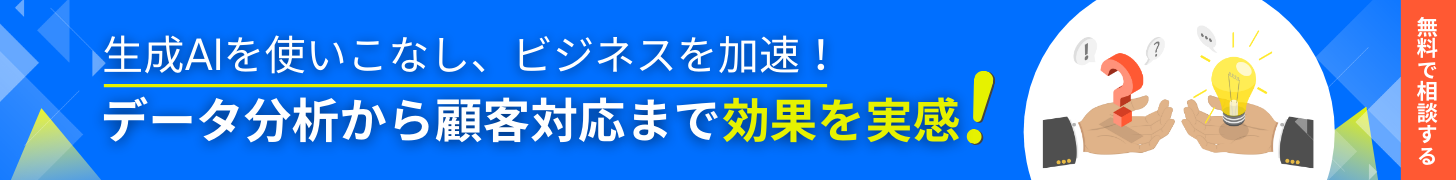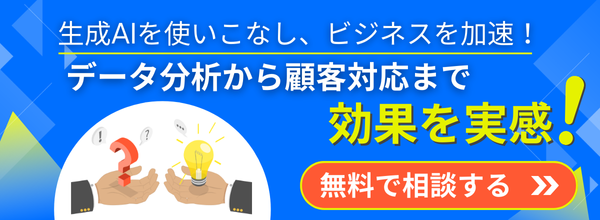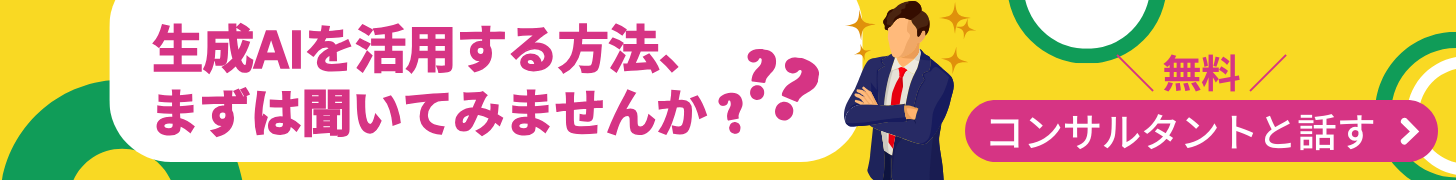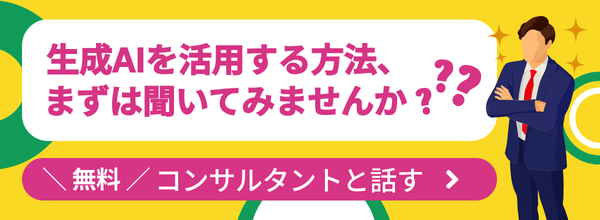LLMのハルシネーションを防ぐには?原因・対策・最新AIモデル動向を徹底解説
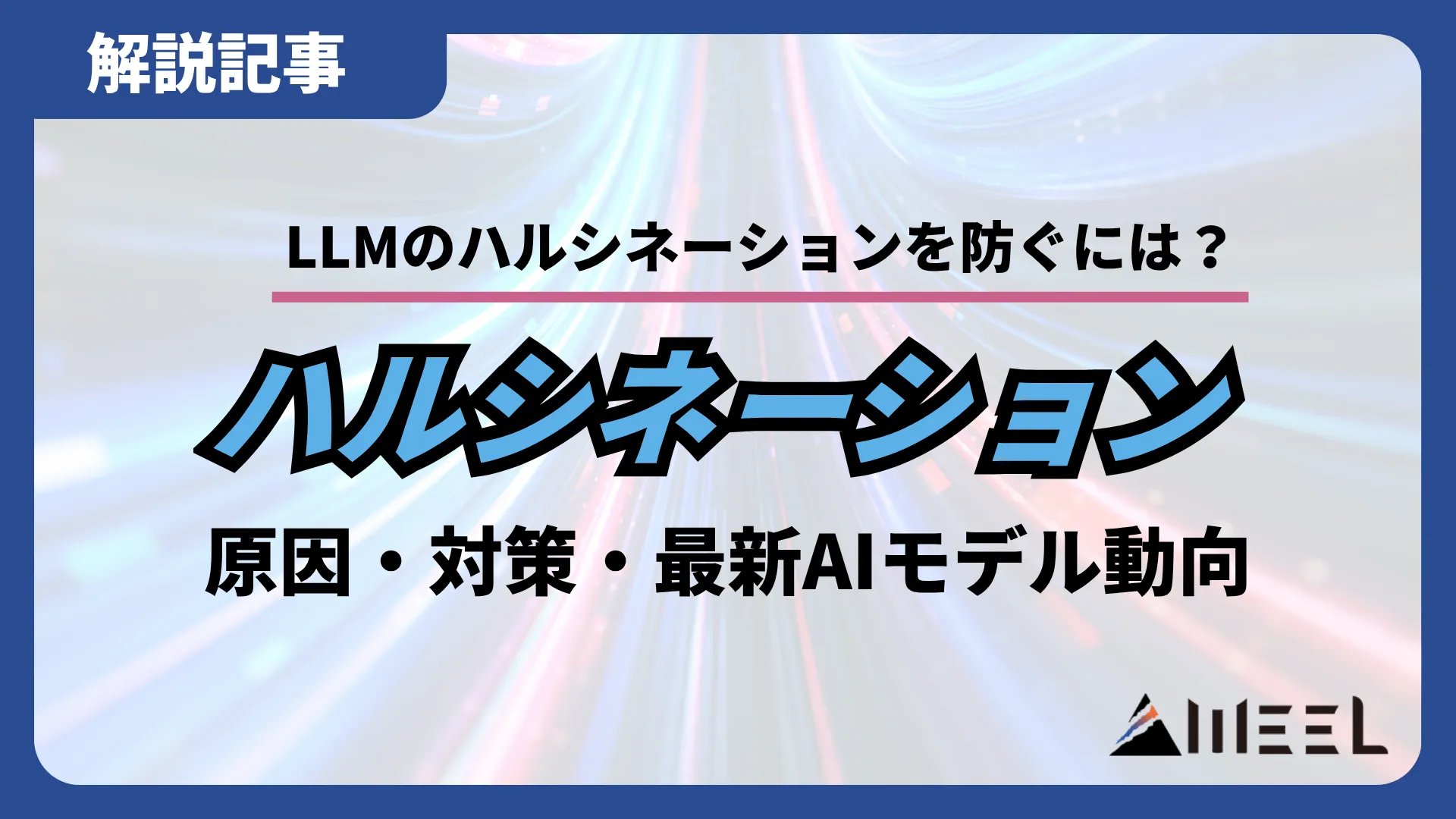
- 2025年最新のAIモデル(GPT-4.5やClaude 4、Gemini 2.5など)は、ハルシネーション発生率が下がり、企業活用の信頼性が向上。
- RAGや自己修正型AIなどの対策が進化し、プロンプト設計・社内ルール整備・ログ管理など実践的な運用ノウハウが充実。
- ハルシネーションの完全防止は困難なため、人間によるチェック体制やFAQ形式で使い方を周知し、リスクを最小限に抑えることが重要。
ChatGPTなどのLLMが嘘の情報を出力してしまうハルシネーションは、企業でLLMを利用する上で重大な問題になりかねません。ハルシネーションにより、企業の信頼を損なうだけでなく、法律上の問題が発生するリスクもあります。
そこで、LLMの論文である「Do Language Models Know When They’re Hallucinating References?」では、「LLMがハルシネーションを自覚し、それを利用してハルシネーションを減らせる」ことが示唆されています。この論文の技術を上手く活用すれば、ハルシネーション問題が解決できるかもしれません。果たして、それだけでハルシネーションの問題を解決できるのでしょうか?
LLMだけではハルシネーションを解決できないのか?
昨今よく議論されているLLMの問題点として、ハルシネーションが挙げられます。ハルシネーションとは、簡潔に言うと「LLMが噓の情報を出力する」という問題です。
本研究では、このハルシネーションの問題に焦点を当てて、ハルシネーションの原因や対策法を見つけるための実験が行われました。本研究における調査対象・目的は、以下の通りです。
- LLMがハルシネーションを起こす原因
- ハルシネーションに対する対策法
- LLMが自身のハルシネーションを、自分で気づけるかどうか
これらを目的として、著者らは「LLMによって生成されたデータの事実と一貫性」のチェックを行いました。その結果、ハルシネーションを改善するために、LLMの生成パイプラインを見直すことが重要であることが分かったのです。
ハルシネーションとは?
ハルシネーションとは、LLMが「噓の情報」を出力してしまう問題のことです。
LLMによって出力された噓の情報は、文献レビューや論文レビューなどのアプリケーションに影響を与えるだけでなく、医学のような分野においても害を及ぼす可能性があるため、LLMを使用する際の問題となっています。
なお、ハルシネーションについて知りたい方はこちらをご覧ください。
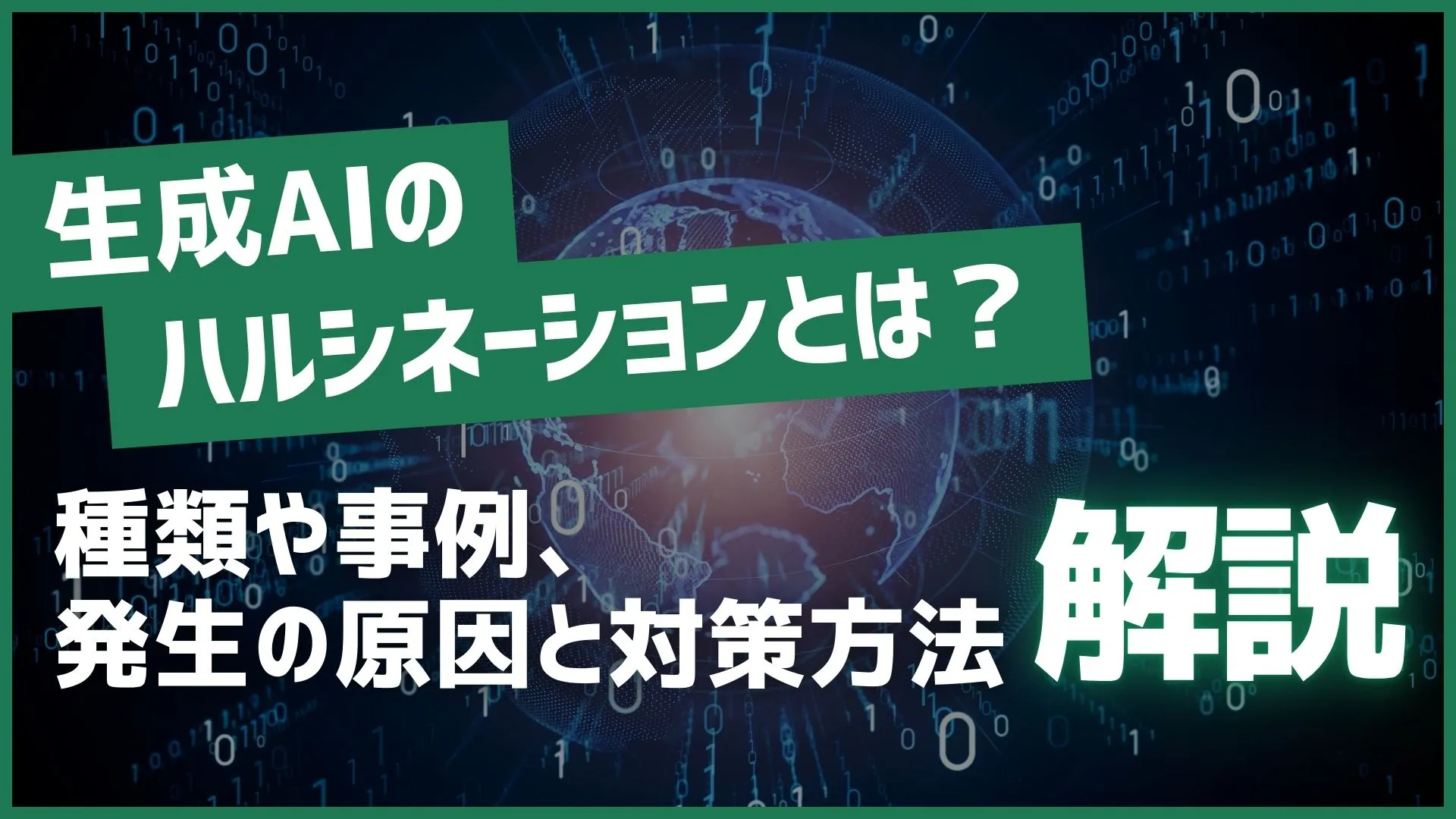
ハルシネーションが発生する理由
AIは、インターネット上の文章を読み込んで学んでいます。その学習の仕組み自体は「次にどんな言葉が続くか」を当てることがメインです。言い換えれば、パズルのピースをはめるように、一番自然に見える答えを組み立てるわけです。
しかし、この方式には弱点があります。質問の背景や細かいニュアンスをAIが正確につかめないことがあるため、「らしきもの」を自信満々に返してしまいます。例えば、学習に使われたデータに含まれていない情報や、指示があいまいすぎるケースでは、AIが「知らないけれど、こう書けば成り立つかな?」と勝手に想像して回答を作り上げてしまうのです。
結果として、事実とズレた回答や、まったく存在しないデータをあたかも本物のように提示してしまう。それが「ハルシネーション」です。仕組み上ゼロにするのは難しいのですが、AIの得意・不得意を知り、回答の裏付け(出典や具体例)を確認することで、リスクを減らすことは可能です。
ChatGPT・Claude・GPT-4など主要モデルの比較
AIモデルを選ぶときは「どれだけ正確に答えてくれるか」、つまりハルシネーションをどれくらい抑えられるかも大切なポイントです。ChatGPT、Claude、GPT-4シリーズをハルシネーションの出やすさと、その対策機能に注目して比べてみましょう。
| モデル | ハルシネーション傾向 | 主な対策機能 | 向いている用途 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT (GPT-4o) | 中程度 | ユーザーとの対話で逐次修正、外部ツール連携 | 日常会話やアイデア出し、程よい正確さが必要な場面 |
| Claude 4シリーズ | 低め | システム・ユーザーメッセージで厳格なガードレール | 長文レポートや法務ドキュメント、リスク管理 |
| GPT-4.1/4.5 | やや高め(専門外質問で注意) | リトリーバル強化(外部知識検索)、詳細プロンプト | コード生成や技術文書、専門的な説明 |
それぞれのモデルは、「次に来る言葉予測」のクセや、設計段階で組み込まれた安全機構の強さが違うため、ハルシネーションの起こりやすさにも差があります。
Claude 4シリーズは最初から安全性を重視する設計で、システムメッセージを使った防護柵が強力。GPT-4.1/4.5はコード生成など正確性が求められる場面で高性能ですが、専門外の内容では「知らない分野を埋めよう」として誤情報を出すことがあるので、注意が必要です。
日常的な対話やアイデアを生み出すにはChatGPTがお手軽ですが、長文レポートや法務文書ではClaude、技術的ドキュメントやプログラミングではGPT-4.1/4.5と、目的に合わせてハルシネーション対策も考慮しつつ使い分けてみてください。
最新のハルシネーション対策とAIモデルの動向
2025年になっても、「ハルシネーション」は依然として気になるポイントです。しかし最近のモデルや技術を使えば、そのリスクを下げることができます。
例えば、OpenAIのGPT-4.5やAnthropicのClaude 4シリーズ、GoogleのGemini 2.5などは、推論能力や感情的知能の向上とともに、間違いを出す確率が1〜2%程度まで抑えられるようになってきました。
RAGも進化しています。リアルタイムでウェブ検索できるだけでなく、文章や画像、音声データも参考にしたり、自分で答え直す「自己修正」機能が付き、実務で使うときの安心感が増しています。
LLMにあらゆる質問をして一貫性を評価
冒頭で紹介した研究では、「あらかじめ用意しておいた質問テンプレートをLLMに投げかけ、その回答の内容を評価する」という実験が行われました。
具体的な実験の手順としては、以下の通りです。
- 質問テンプレートをLLMに投げかける
- さらに詳細な質問を投げかける
- 回答の内容(ハルシネーションか否か)を評価
あらかじめ質問テンプレートを用意しておき、それらの質問をLLMに投げかけます。
次のステップでは、先ほどの質問に関連する、より詳細な複数の質問をLLMに投げかけます。こうすることで著者らは、どのような質問がハルシネーションを引き起こすのか、その原因を探ろうとしました。
そして、その質問へのLLMの回答に対して、以下の観点で評価をしています。
- 回答の一貫性
- 回答の事実性
また本研究では、回答の生成や評価において、以下の3つのLLMが使用されています。
- GPT-3 (text-davinci-003)
- ChatGPT (gpt-35-turbo)
- GPT-4 (gpt-4)
さらに、上記のLLMが生成した回答の事実性を確認するために、「Bing Search API」を使用しています。Bing Search APIとは、Microsoftの提供する検索エンジンであるBingでの検索結果を取得するためのAPIのことです。
そして、もしBing検索にヒットすれば、「LLMの出力内容に事実性があり、ハルシネーションは起きていない」という認識になるのです。
ハルシネーションを減らすには生成パイプラインの改善が有効ということが明らかに
本研究の結果として、ハルシネーションを起こした情報を、確実に特定できることが分かりました。ただし、実験の詳細や数値、定性的な知見は論文の中で論じられているが、具体的な定量的結果は本稿内では述べられていません。
そのため、本当に本手法が有効なのか客観的にはわからない点に注意が必要です。
また、筆者らは、「ハルシネーションの削減には、生成パイプラインの変更が有効」だと結論付けました。生成パイプラインとは、「LLMが文章を学習し、それをもとに文章を生成する」までのプロセスのことです。
要するに「モデルの構造自体を工夫して変えろ」ということだと筆者は理解しています。本論文で述べられているハルシネーションを削減するための工夫ポイントは、以下の2点です。
- LLMに対して、必ず「実在する情報」から引用させる
- LLMが生成した文章の事実確認をして、必要ならば修正する
なお、ChatGPTについて知りたい方はこちらをご覧ください。
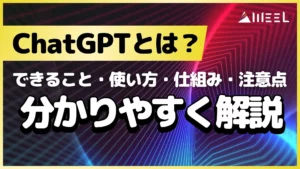
ハルシネーション対策の分類整理
ハルシネーションを減らす手段は、大きく三つに分けられます。
- プロンプト工夫
指示文をできるだけ具体的にすると、AIは迷わず答えを組み立てやすくなります。例えば「◯◯について簡潔に説明し、根拠を3つ挙げてください」のように詳細を盛り込むと、誤った情報が入り込みにくくなります。 - RAG(外部知識参照)
AIが回答を作る前に、信頼できるウェブ情報や社内データベースを検索してから答える仕組みです。最新データを取り込みながら答えるので、そもそもの前提が間違っている確率を下げられます。 - モデル自体の改善
学習に使うデータの質を上げたり、アルゴリズムの調整を行ったりして、元からハルシネーションを起こしにくいモデルを作る方法です。時間やコストはかかりますが、最も根本的な対策と言えます。
これらを組み合わせることで、より信頼性の高いAI活用が実現できるでしょう。
実験や論文による自己検出能力の紹介
最近では、AI自身が「この回答、大丈夫かな?」と気づけるかどうかを調べる研究が増えています。※1
MISRという枠組みでは、AIに間違いを見つけさせるタスクを与え、「自分が怪しいと思う箇所」をマークできるかを測定します。ある実験では、GPT-3.5 Turboが自分のハルシネーションをおよそ58%の確率で検知できたという結果も報告されており、AIの“自己チェック力”向上が信頼性アップの鍵とされています。
ハルシネーション対策精度の定量比較
対策を行った場合の効果を数字で見ると、その違いは一目瞭然です。
例えばRAG-HATという手法を使うと、これまでよりハルシネーション発生率を最大約40%も減らせたというデータがあります。モデルごとの比較では、ChatGPT-4が他モデルと比べて元々ハルシネーション率が低く、追加対策の効果も大きい傾向が見られます。※2
こうした数値を参考にすれば、自社に合った対策レベルを検討しやすくなるでしょう。
エンタープライズ向けの対応例
企業で安心してAIを使うには、出力内容の裏付けや操作履歴の管理が欠かせません。
具体的には、以下の2つが挙げられます。
- ログ管理
どんな入力をいつ行い、どんな出力が出たかをすべて記録し、安全な倉庫で保管。 - 類似度スコアUI
AIの回答と正しい情報を自動で比べ、どのくらい似ているかをスコア表示。ユーザーは「この回答は80%信頼できる」と一目で把握できます。
これらを組み合わせることで、誤情報をそのまま業務に流用してしまうリスクを抑えられます。
プロンプト例・実践的テンプレート
すぐに使える、シンプルな指示文の型をご紹介します。
- 「最新の公的データを参考に、◯◯を200字以内で要約してください」
- 「不明な点があれば『わかりません』と答えてください」
- 「回答には必ず情報源(URLまたは文献名)を明記してください」
こうしたルールをプロンプトの冒頭に置くだけで、AIは「根拠を示す」「不確かなものは避ける」よう意識してくれます。
ビジネス導入時の社内ルール整備とチェック体制
AIを本格的に業務に組み込む前に、社内ルールやガイドラインを整えておくと安心です。
具体的には、以下4点に気を付けると良いでしょう。
- 利用範囲の明確化:どの部署が、どのAIサービスを、どんな用途で使うかを定義する。
- 入力データの制限:個人情報や機密情報の取り扱い基準を設定。
- 出力チェック手順:必ず人間が事実確認を行うフローを決め、AIの回答だけで業務を進めない。
- 教育・研修:定期的にハルシネーションや漏えいリスクについて社員に周知し、チェック方法を訓練する。
こうした仕組みがあると、「AIが出したから安心」という過信を防ぎ、安全性を保てます。
対策の限界と今後の課題
どれほど工夫しても、AIのハルシネーションを完全にゼロにするのは難しいのが現実です。AIはあくまで「予測」で答えているため、未知の情報や曖昧な質問には弱く、人間のような確かな判断力はまだ持ち合わせていません。
今後は自己検出力の強化や、外部情報との連携精度アップが進むでしょうが、最終判断は必ず人間が行う体制を崩さないことが大切です。AIは強力な道具ですが、使いこなすための「人の目」を忘れずに進めましょう。
よくある質問
生成AIを使い始めるときによくある疑問とその答えをまとめました。生成AI導入に関する不安を解消するため、導入前に知っておくと安心です。
重大なハルシネーション対策に有用か
この研究で提案されたのは、ズバリ「ハルシネーションの自己検出」のための手法でした。
ハルシネーションの問題が注目されている昨今において、非常に興味をそそられる内容だったと思います。ハルシネーションは特に有害であり、及ぼす影響も大きいので、こういった類の技術は早く実用可能になって欲しいです。
しかし、本研究には以下のような問題点があるのではないかと思います。
- 事実検証をBingの検索エンジンに頼りすぎていること
- 3つの特定のLLMに焦点を絞っているため、LLM全般に言えることか不明であること
今後の研究では、これらの問題点を克服し、提案された手法の妥当性を向上させることを目指すべきかなと感じます。
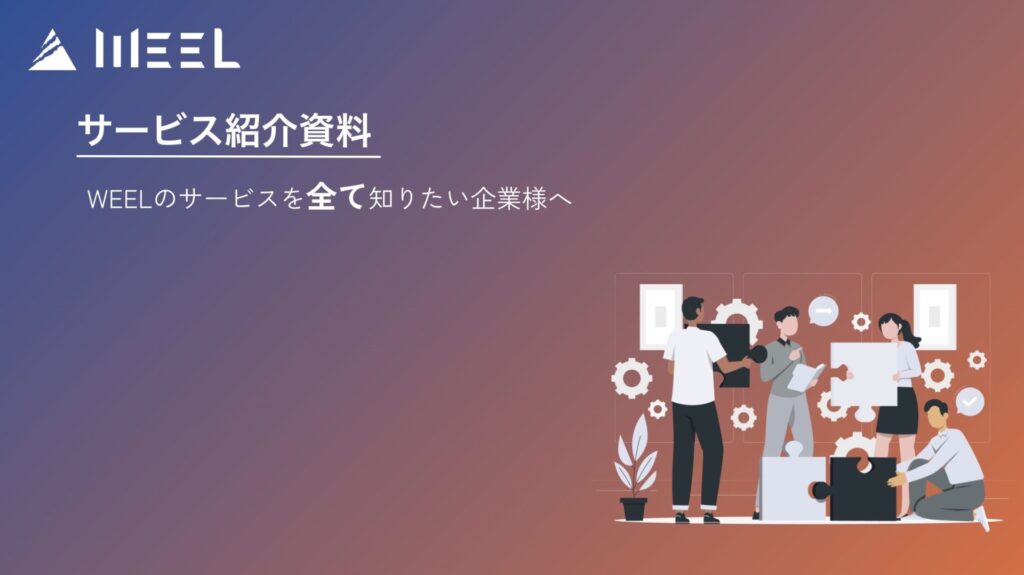
生成系AIの業務活用なら!
・生成系AIを活用したPoC開発
・生成系AIのコンサルティング
・システム間API連携
最後に
いかがでしたでしょうか?
2025年現在、LLMのハルシネーション対策は大きく進化し、最新モデルや実践的な運用ノウハウも充実してきました。AIを安心して活用するためには、技術だけでなく、社内ルールや人のチェック体制も大切です。
自社の業務や目的に合ったAIの使い方を、ぜひ一緒に考えてみませんか?
AIの導入やハルシネーション対策でお悩みの方は、ぜひWEELにご相談ください。WEELでは、最新AI技術の活用方法や業務効率化のノウハウ、導入支援まで幅広くサポートしています。
AIの基本から実践的なツール活用、社内展開のご相談まで、お困りごとは何でもお気軽にお問い合わせください。
株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!
開発実績として、
・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント
・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット
・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト
・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール
・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用
・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント
などの開発実績がございます。
生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。
➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。
まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。
➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。
セミナー内容や料金については、ご相談ください。
また、大規模言語モデル(LLM)を対象に、言語理解能力、生成能力、応答速度の各側面について比較・検証した資料も配布しております。この機会にぜひご活用ください。