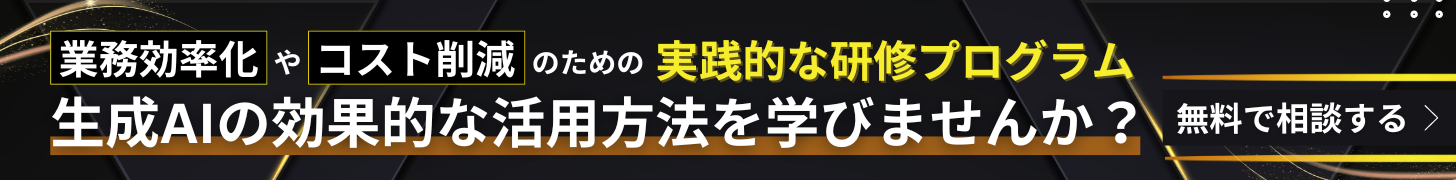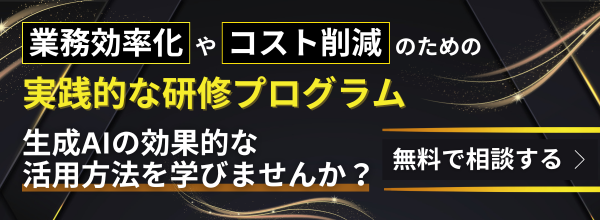生成AI導入前に読むべき!生成AI開発企業おすすめ10社と依頼時のポイントを解説
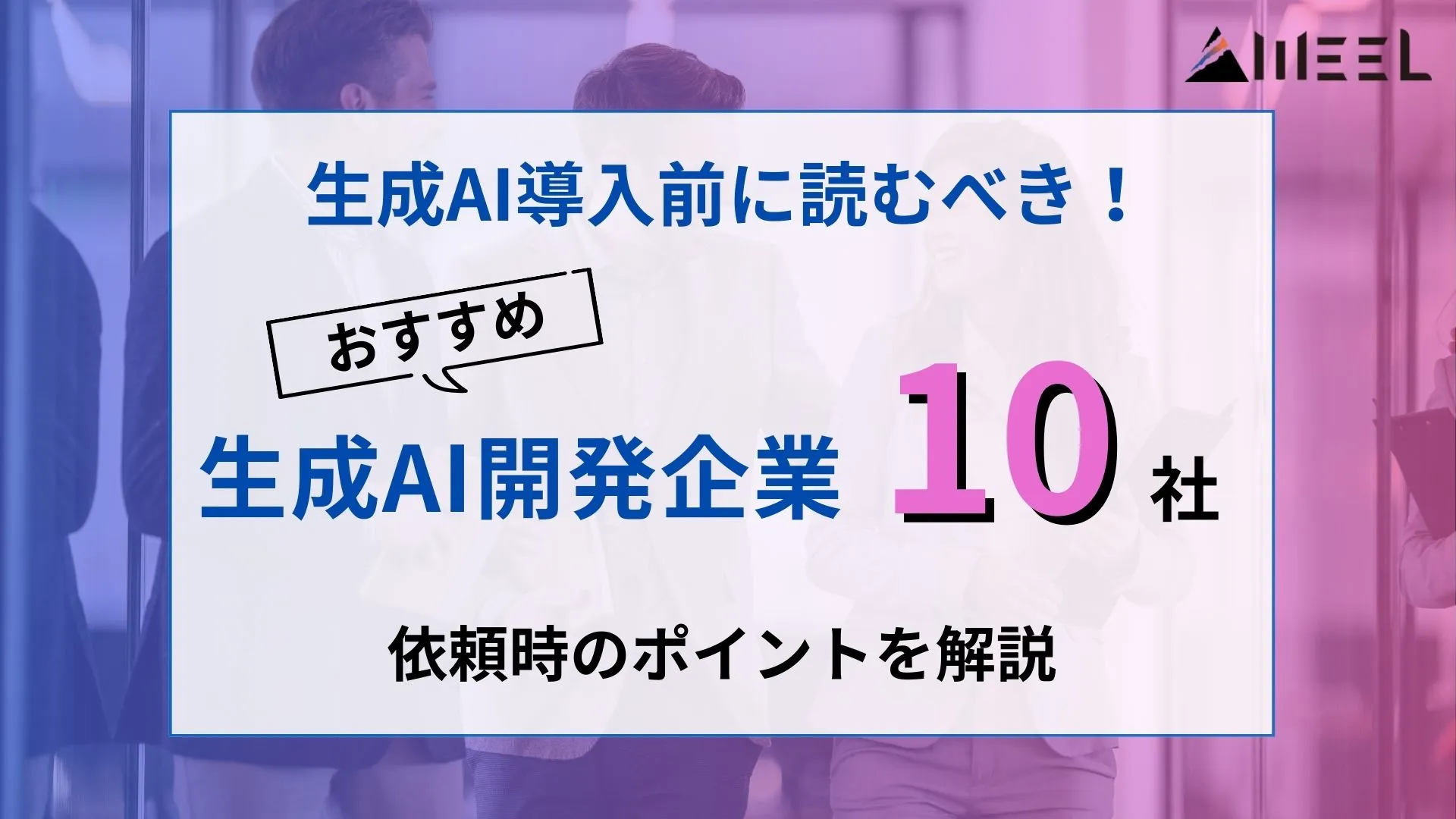
- 生成AIの導入は、要件定義から運用まで支援できる専門企業への依頼が成功の鍵。
- PoCや本開発を短期間で進められ、自社に最適な提案が受けられるのも大きなメリットである。
- 導入目的やデータ状況を事前に整理することで、スムーズで無駄のない開発が実現できる。
近年、ChatGPTをはじめとした生成AIが凄まじい勢いで進化していることにより、生成AIを業務利用する企業が増え、業務効率化やビジネス革新が急速に進んでいます。
そんな中、生成AIを本格的に活用するには「信頼できる開発企業」の選定が極めて重要です。
本記事では、生成AI開発企業おすすめ10社や生成AI開発企業に依頼するメリットなどについて詳しく解説します。これから生成AIをビジネスに導入したいと考えている企業にとって有益な情報を網羅的に解説しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/
生成AI開発企業とは?
生成AI開発企業とは、ChatGPTなどの生成AI技術を活用し、企業の業務改善や新規事業創出を支援する専門ベンダーです。
要件定義からPoC、本開発、保守運用まで一貫して支援する企業も多く、業種・業界に応じた最適なAIツールを開発することが可能です。
そもそも生成AIとは
生成AIとは、文章・画像・音声などを生成するAI技術の総称で、大規模言語モデル(LLM)や生成画像モデルなど、さまざまな種類があります。
代表的なツールで言うと、ChatGPTやClaude、Geminiなどがあり、文章生成、コード作成、画像生成、要約・翻訳などさまざまな分野のタスクをこなすことができます。
なお、生成AIについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

従来AI開発との違い
従来のAIは、分類・予測・異常検知などで利用されることが多く、限られた業務のみに特化したツールとして一般的に普及していました。
一方、生成AIは、文章生成、コード作成、画像生成、要約・翻訳など、入力されたプロンプトに沿ってさまざまな出力を行うことができます。
生成AI開発企業おすすめ10選
生成AI導入を効果的に行うためには、信頼できる生成AI開発企業を選ぶ必要があります。次に、おすすめの生成AI開発企業を10社紹介します。
株式会社WEEL

株式会社WEELは、生成AIのコンサルティングと受託開発を行う生成AIに特化した専門企業です。※1
RAG技術を活用した「受注AIエージェント」など、非定型業務の自動化に強みを持ち、実務に直結した導入支援を行っています。
また、メディア運営にも注力しており、技術力だけでなく生成AIを活用するための実用的なサポート体制が整っているのもポイントです。
株式会社ABEJA

株式会社ABEJAは、自社PaaS型AI基盤である「ABEJA Platform」を中核に、AI・生成AIモデル(ABEJA LLM Series)の導入、運用、倫理・ガバナンス構築を一貫して支援しています。※2
2022年には13Bパラメータ日本語LLMを発表し、300社以上のDX実績をもとに、業務プロセス全体を最適化します。
株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズは、企業向けAIプラットフォームである「exaBase」を中心に、「Products」「AI Assets」「Consulting Services」を統合的に提供しています。※3
法人向けChatGPTの「exaBase 生成AI」は国内市場シェアNo.1を獲得し、2025年7月時点で10万人以上の利用者と月2,500人分の業務時短実績があります。
株式会社ブレインパッド

株式会社ブレインパッドは、生成AI技術と自社開発の高度なレコメンド技術を融合した対話型検索サービスである「Rtoaster GenAI」を提供しており、感覚的・自然なキーワードから検索できる「あいまい検索」に対応しているのが特徴です。※4
そのため、ECや不動産など、さまざまな業界で導入が進んでいます。
株式会社AIdeaLab
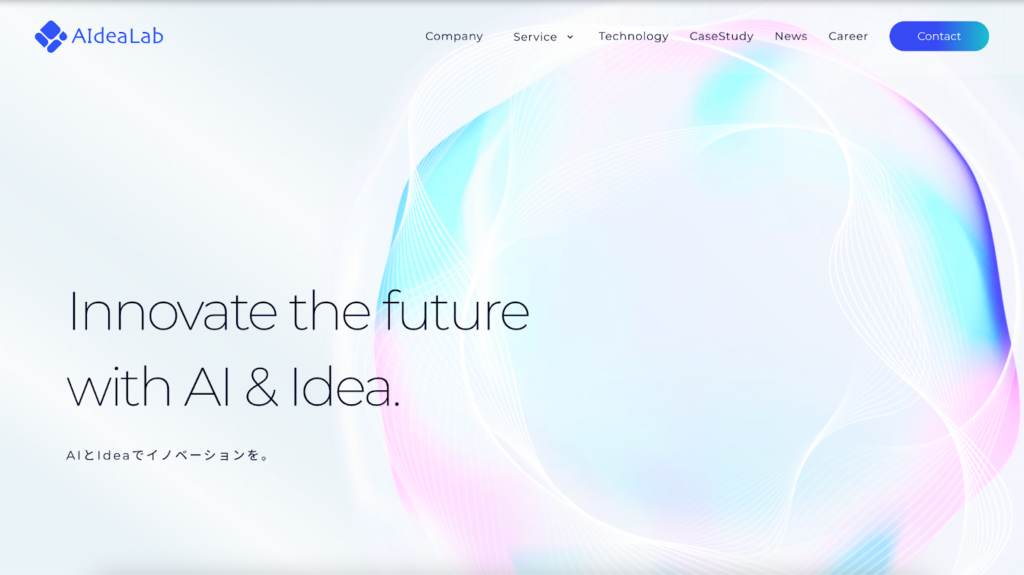
株式会社AIdeaLabは、生成AIを活用した新規事業開発や業務効率化のカスタマイズ支援を提供するAIベンチャー企業です。※5
日本語対応の動画生成AIである「VideoJP」や社内向けChatAIなど、先進的なプロダクトを次々に開発していることから、柔軟な開発体制と高い実装力が強みです。
株式会社マクニカ
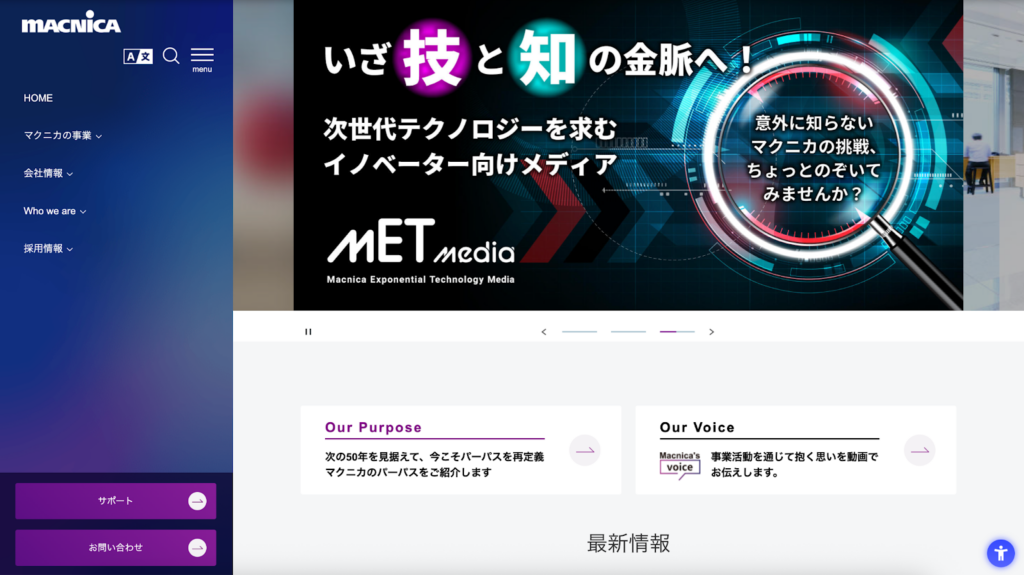
株式会社マクニカは、セキュリティと連携した生成AIソリューションを強みに持つITインテグレーターです。※6
AIの信頼性評価を行う「DeepKeep」や、個人情報の匿名化ツール「Private AI」などを提供しており、GMOとの協業によるGPU基盤の活用支援にも注力しています。
株式会社KICONIA WORKS
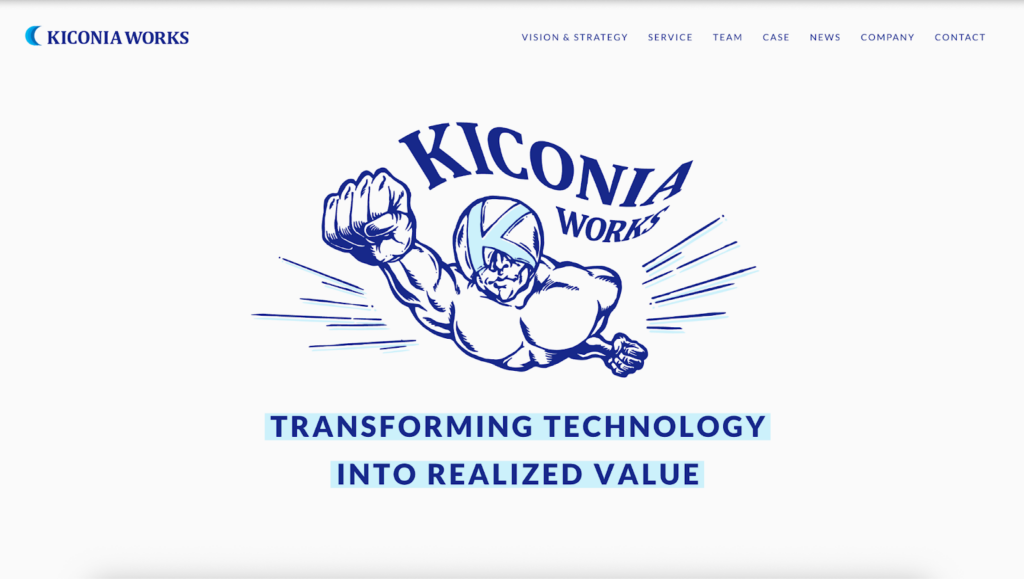
株式会社KICONIA WORKSは、2018年に設立されたAIベンチャー企業で、日本語特化の独自LLMの研究や、業務プロセスに合わせた生成AI導入の支援を行っています。※7
また、社内でのLLM+RAGの研究やコンテンツ生成案件の実績を活かし、高精度かつ柔軟な生成AIを提案することが可能です。
株式会社オプティム

株式会社オプティムは、農業や医療、建設などの現場業務に特化した生成AIソリューションを提供しています。※8
農業ではドローンとAIによる害虫散布の「Pinpoint Time Spraying」を全国規模で展開し、建設現場では写真撮影をもとに報告書を自動生成する「OPTiM Taglet」などを展開しています。
医療分野のオンプレミス型生成AIである「OPTiM AIホスピタル」は、高セキュリティを確保しながらカルテや看護サマリー作成を支援することができるため、時間削減を実証しています。
富士通フロンテック株式会社
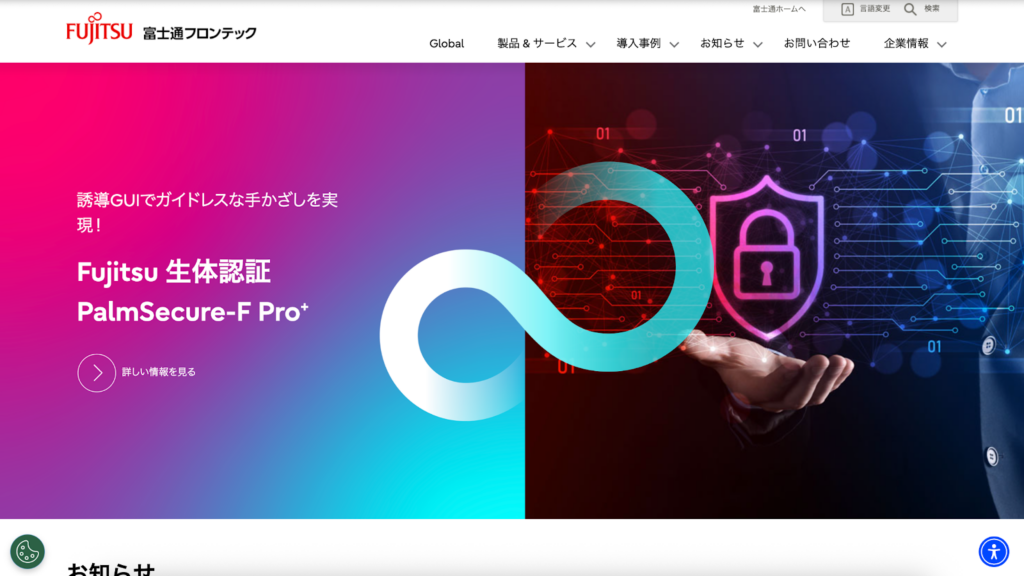
富士通フロンテック株式会社は、公共インフラや小売業界向けに生成AIを活用したソリューションを多数展開する企業です。※9
店舗向けAIチャットボットである「TeamConnect」による業務支援や、店内不審者検知など、現場業務の効率化とセキュリティ強化に実績があります。
また、生成AIの安全運用を支える「Generative AI Platform」を2025年度から提供しており、機密性の高い業務にも対応可能です。
株式会社Preferred Networks
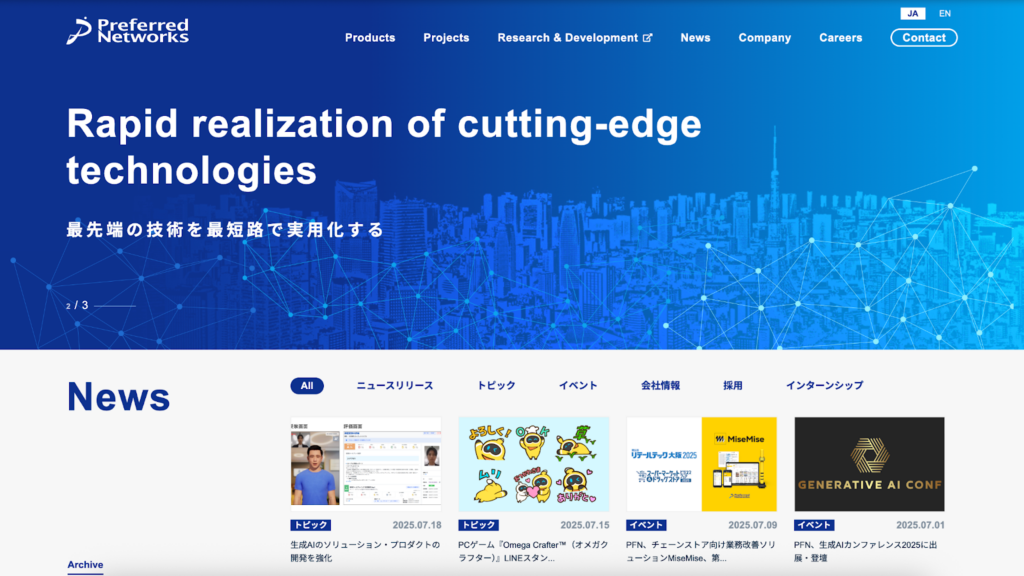
株式会社Preferred Networksは、日英両言語対応で性能が世界トップクラスの国産大規模言語モデルである「PLaMo」を開発した企業です。※10
業界特化型モデルやInsight Scan・Talent Scouterなどの「PreferredAI」は、自治体や企業で導入実績も豊富で、AI半導体「MN‑Core」の開発やクラウド基盤強化にも力を入れており、生成AIの研究から社会実装までを一気通貫でサポートしています。
生成AI開発企業に依頼する5つの主なメリット
生成AIの活用が注目される今、自社での内製化にこだわらず、生成AI開発企業に依頼する企業が増えています。
次に、生成AI開発企業に依頼することで得られる5つの主要なメリットを解説します。
①専門的な技術力と最新知識を活用できる
生成AI開発企業は、LLMをはじめとした先端技術に精通したエンジニアを抱えており、OpenAIのGPTシリーズやGoogleのGemini、MetaのLLaMA系などのグローバルモデルだけでなく、ELYZAやrinnaといった日本語特化型モデルにも柔軟に対応できる技術力を持っています。
また、複数のモデルを比較・評価しながら、目的に応じた最適な技術選定やカスタマイズなどの提案も可能なため、さまざまな角度から最適な生成AIを開発することができます。
②PoC(試験導入)や本開発を短期間で実現できる
生成AI開発企業には、豊富な導入実績があり、要件定義からPoC、学習・チューニング、評価までをスムーズに展開することができます。
そのため、プロジェクトによっては、わずか2〜3ヶ月でプロトタイプを構築し、経営判断や現場適用の足がかりとすることも可能です。
③データ設計から運用・改善までワンストップで支援してくれる
生成AI開発企業へ開発を依頼すると、前処理を含めたデータ設計や導入後の運用改善、再学習、MLOps環境の構築までを一貫して行うことができます。
さらに、業務フローへの定着を見据えた社員研修やマニュアル整備も含めた「運用まで見据えた伴走支援」が期待できます。
④セキュリティ・コンプライアンス面でも安心できる
生成AIの導入において、情報漏洩や著作権、プライバシーのリスク対策が不可欠ですが、多くの生成AI開発企業ではPマークやISO27001取得のほか、医療や金融業界向けのコンプライアンスなどに配慮されていることがほとんどのため、セキュリティ・コンプライアンス面でも安心できます。
⑤自社の業界・業務に特化した最適な提案が得られる
生成AI開発企業の中には、製造・金融・小売・教育・自治体など特定の業界に特化した企業も多いため、自社の業界・業務に特化した最適な提案を得ることができます。
例えば、製造現場向けには「作業指示文書の自動生成+音声読み上げ」など、現場のリアルな状況を想定したAIツールの開発が可能です。
発注前に整理すべき5つのポイント
生成AI導入を成功させるには、生成AI開発企業の選定だけでなく、発注側の準備も大切になってきます。
ここでは、開発を依頼する前に整理しておきたい5つの重要なポイントを解説します。
①解決したい業務課題と導入目的(ゴール)
まず明確にすべきなのは「なぜ生成AIを導入したいのか?」という点についてです。考える際には、現場で直面している業務課題とその解決によって得たい成果をセットで考える必要があります。
例えば、業務課題が「問い合わせ対応の工数を削減したい」という場合「チャットボット導入で対応時間を30%短縮」という数値を盛り込んだ明確な目標を設定しましょう。
目的があいまいだと、ツールの選定や仕様も曖昧になってしまうため、事前に解決したい業務課題と導入目的をしっかり考える必要があります。
②想定ユーザーと利用シーンの整理
次に考えるべきは「誰が・どこで・どう使うのか」という具体的な利用イメージで、UI設計やモデル選定にも影響する重要な要素です。
例えば、社内マーケティング担当者がLP原稿を毎週自動生成するというケースと、エンドユーザーが音声でFAQに問い合わせるケースでは求められる機能も大きく異なります。
そのため、事前に想定ユーザーや利用シーンについても明確にすることで、より利用しやすいAIツールを開発することができます。
③必要な機能と優先度(MoSCoW分析)
プロジェクトの初期段階では「すべての機能を完璧に作る」よりも、まずは最小限の要件を満たすことから始めることが重要です。
その際に有効なのが、MoSCoW分析です。
MoSCoW分析とは、要件をMust(対応必須)、Should(対応すべき)、Could(できれば対応)、Won’t(対応不要)という4つの分類で評価し、プロジェクトで対応する要件の優先順位を決める方法のこと。
例えば「プロンプト入力」「日本語生成」はMust、「ChatGPT API連携」はShould、「自動要約」「多言語対応」はCouldというように機能を分類することで、より確度の高いAIツールの開発を行うことができます。
④データと学習素材の状況
生成AIの精度は、学習に使えるデータの質と量に大きく左右されます。
そのため、自社でどのようなデータが保有されているかを確認し、使えるデータの抽出や必要に応じて権利関係や個人情報の取り扱いについても確認を行いましょう。
例えば、過去のFAQログやカスタマー対応履歴、商品スペック表など、独自の情報はより精度を高めるためには必要不可欠な情報となるでしょう。
また、データが少ない場合は、Few-shotやZero-shot前提の構成を考える必要があります。
⑤予算・スケジュール・導入スコープ
予算や希望納期、導入スコープを事前に明確にしておくことで、生成AI開発企業との意思疎通がスムーズになります。
例えば、まずはPoCから始めて「初期費用100万円以内/期間2ヶ月」でトライアル導入し、その結果をもとに「本導入500万円/期間6ヶ月/3年運用前提」で拡張するなどといったようなスケジュールを明確にしておく必要があります。
導入ステップ別ロードマップ(0→12ヶ月)
生成AIを現場で定着させるには、段階的な設計と実践が不可欠です。次に、PoCから運用改善まで、成果を出すためのロードマップについて解説します。
PoC(0‑3ヶ月)
最初の3ヶ月は、導入目的の明確化とユースケース選定、PoC設計を行います。
まずは目的・KPIを現場視点で設定し、対象業務を棚卸して優先順位をつけていきます。
その後、小規模なプロトタイプを構築し評価軸を定め、結果を社内へ共有しながら本開発前に方向性を決めていく必要があります。
本開発(4‑9ヶ月)
PoCの成果を踏まえて、必要機能をMoSCoW分析で優先順位化し、本開発を進めていきます。
モデルの精度向上・UI設計、テストとユーザーからのフィードバックを繰り返しながら改善していきます。
また、並行して社内教育やガバナンス設計も進め、導入後すぐにツールを最大限に活用できるような体制を整えましょう。
運用・改善(10ヶ月以降)
導入後は、部署ごとの活用事例を集めて社内で共有したり、使い方を学ぶ研修を定期的に行ったり、社内でAIツールが普及するような取り組みが必要です。
また、問題が起きたときの対応方法もあらかじめ決めておいたり、システムの改善や更新を続けていくことで、生成AIの定着率を向上させることができるでしょう。
なお、PoC開発について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。
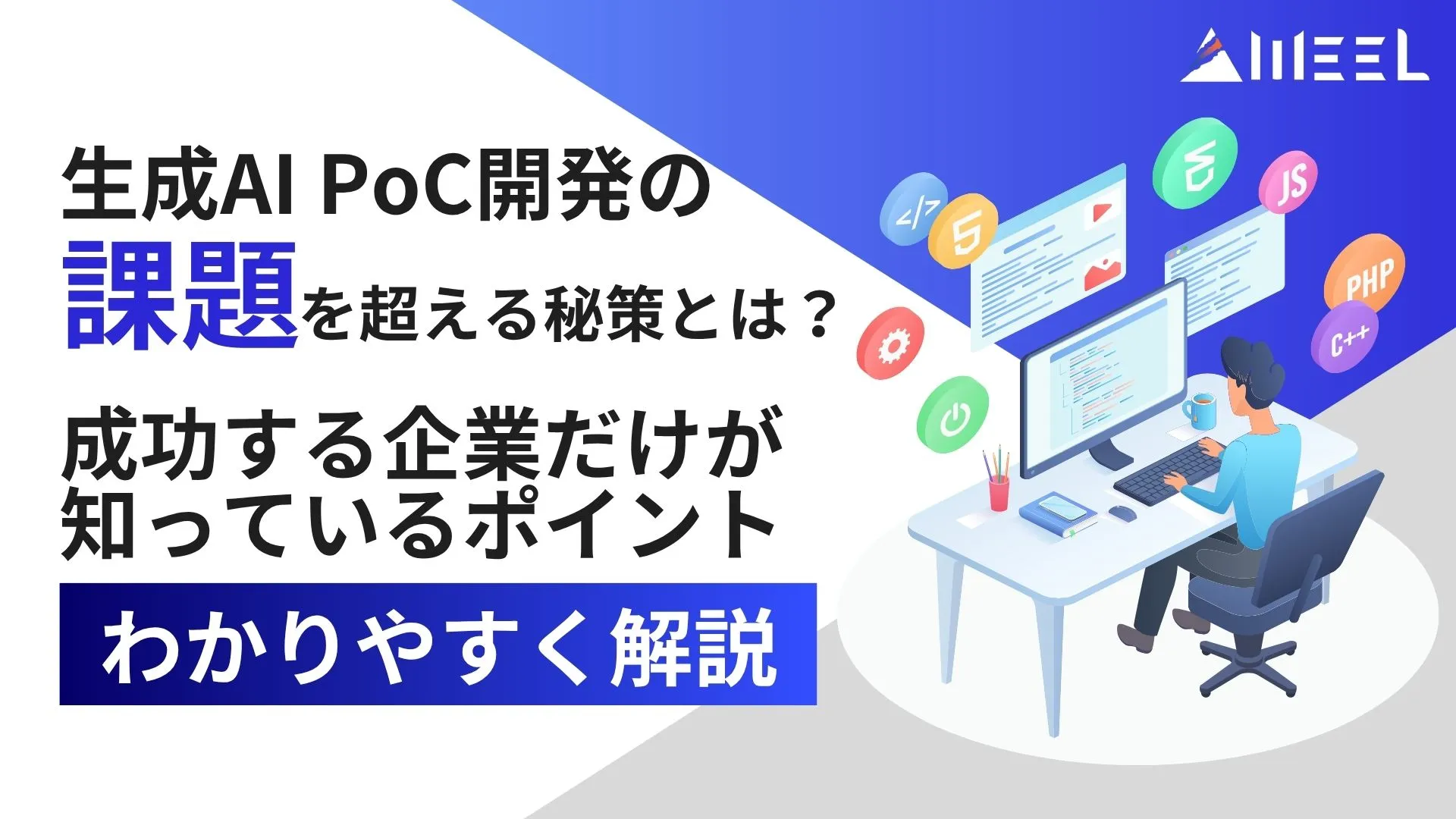
生成AI開発企業の費用相場
生成AIの導入には、開発・運用・拡張といった各フェーズでコストが発生します。
ここでは、各フェーズごとの予算感や費用の目安について解説します。
生成AI開発の予算目安
生成AI開発の予算は、開発の規模や複雑さによって大きく変動します。
例えば、PoCは300万〜500万円、小規模開発では150万〜1,000万円、中規模開発になると1,000万〜3,000万円、大規模開発は3,000万円以上が一般的な目安です。
保守・運用費用の目安
生成AIシステムの保守・運用には、モデルの再学習や性能の最適化、セキュリティ更新などの継続的な対応が求められるため、年間の運用費用として初期開発費用の15〜30%程度が必要となります。
さらに、LLMを利用する場合はトークン数に応じたAPI利用料が発生するケースもあり、運用規模に応じた柔軟な予算設計が重要です。
追加開発・カスタマイズの費用目安
生成AIの導入後は、現場のフィードバックをもとに新たな要件が生まれることも多く、追加の開発費用が発生する可能性があります。
小規模なUI変更や設定調整であれば100万〜300万円程度で、機能追加では200万〜500万円程度が一般的です。
しかし、大規模な機能拡張やシステム連携などを行う場合は、500万円以上となるケースもあるため、カスタマイズの内容やシステム構成に応じて見積もりを行う必要があります。
なお、生成AIの導入費用について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。
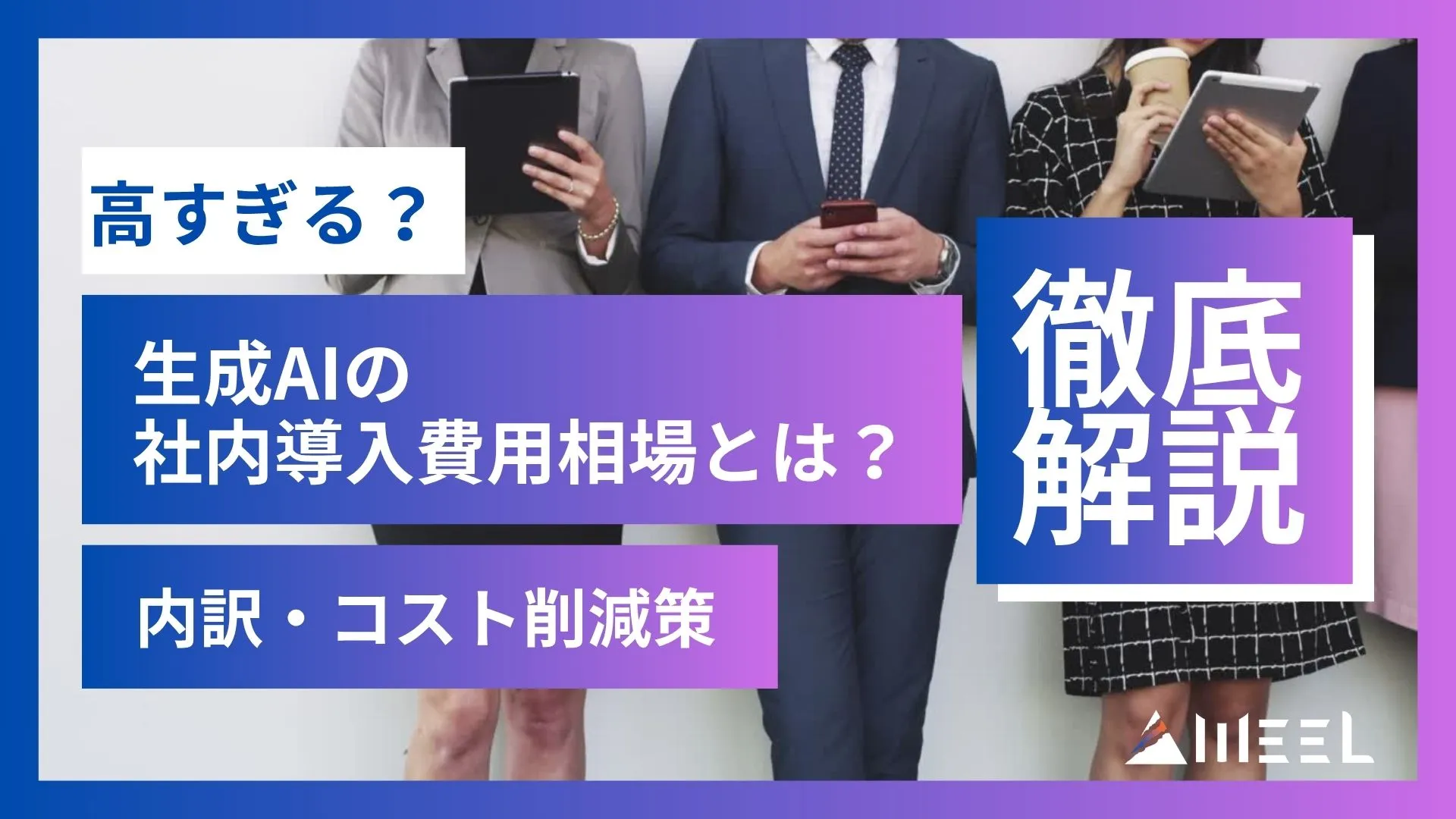
よくある質問
生成AI導入を成功させるために、信頼できる開発企業との連携が鍵
生成AIは、業務効率化や新たなビジネスを創出する際に便利なツールですが、生成AIの効果を最大限に発揮するためには、専門知識を持った生成AI開発企業との連携が不可欠です。
本記事で紹介した企業や導入ステップ、準備のポイントを参考にしながら最適な生成AI開発企業と自社専用ツールを開発することで、生成AIの効果を最大限に発揮することができるでしょう。

最後に
いかがだったでしょうか?
実務に直結する生成AI導入を成功させるには、信頼できるパートナー選びが重要です。最適な活用方法を一緒に検討しませんか?
株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!
開発実績として、
・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント
・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット
・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト
・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール
・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用
・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント
などの開発実績がございます。
生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。
➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。
まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。
➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。
セミナー内容や料金については、ご相談ください。
また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。

【監修者】田村 洋樹
株式会社WEELの代表取締役として、AI導入支援や生成AIを活用した業務改革を中心に、アドバイザリー・プロジェクトマネジメント・講演活動など多面的な立場で企業を支援している。
これまでに累計25社以上のAIアドバイザリーを担当し、企業向けセミナーや大学講義を通じて、のべ10,000人を超える受講者に対して実践的な知見を提供。上場企業や国立大学などでの登壇実績も多く、日本HP主催「HP Future Ready AI Conference 2024」や、インテル主催「Intel Connection Japan 2024」など、業界を代表するカンファレンスにも登壇している。