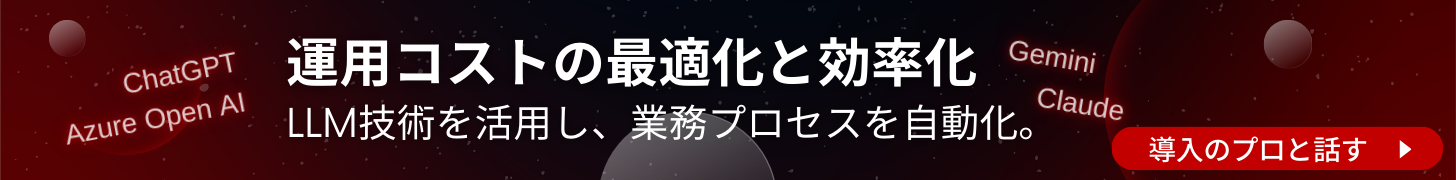ChatGPTを企業利用するリスクと対策6選!実際の企業事例と共に解説

2024年6月現在、ChatGPTはビジネスのあらゆるシーンで活用されてきています。
しかし、ChatGPTを業務に活用する上で、当然情報漏洩や著作権侵害などのリスクも存在します。
そこで本記事では、ChatGPTを企業利用する際のリスク・問題点、およびその対策について詳しく解説します。ぜひ最後まで読んでいただき、リスク対策をした上でChatGPTを活用して業務を効率化してください!
※お時間がない方は、最後のまとめを読めば内容を把握できるようにしてあります。
\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/
ChatGPTを企業利用する6つのリスク
ChatGPTの活用は幅広く、業務効率化や新たなアイデアの作成など多くのメリットがありますが、一方でそれに伴うリスクも存在します。
様々なリスクを理解し、対策を講じることで、ChatGPTをより効果的に活用できます。ChatGPTを利用する上でのリスク・注意点とはどのような事があるのでしょうか?
以下にまとめていきます!
ChatGPTを利用する上で起こりうる具体的なリスクは下記のとおりです。
- 情報漏洩
- 著作権侵害やプライバシー侵害
- 虚偽情報の生成
- 倫理的に不適切な文章を生成
- 社員のChatGPTへの依存
- 悪意のあるプラグインによるアカウント侵害
上記のリスクについて、以下で詳しく解説しますね。
情報漏洩
ChatGPTを業務に導入することで、情報漏洩のリスクがあります。
というのも、ChatGPTに入力した内容がAIモデルの学習に利用される可能性があるからです。実際に、ChatGPTを提供するOpenAI社の公式ページにて、以下のように公表されています。
“API以外のChatGPTとDALL-Eに入力したデータは、モデル改善に使用する場合がある”
つまり、もし機密情報や顧客データなどの重要な情報を入力してしまうと、ChatGPTが悪気なくその情報を拡散してしまう恐れがあるのです。実際に、Amazon社は、サービス開始前のプログラムに似ている内容がChatGPTで生成されたと報告しております。*1
著作権侵害やプライバシー侵害
ChatGPTを業務に導入することで、著作権侵害やプライバシー侵害のリスクもあります。そもそもChatGPTは、インターネット上に既に存在するデータを基に、文章やプログラムを生成するツールです。
そのため、ChatGPTで生成された文章やプログラムが、意図せず既存のものに類似してしまう可能性もあります。
ChatGPTから生成されたデータを外部に公開するときは、以下の2つを必ず確認しましょう。
- 作られたデータが既存の著作物を模倣していないこと
- プライバシーを侵害していないこと
虚偽情報の生成
ChatGPTは、誤った情報を平然と出力する「ハルシネーション」を起こすリスクがあります。ハルシネーションを起こす原因は、下記が考えられます。
- ChatGPTは、インターネット上のテキストデータを学習して文章などを生成するツールであること
- ChatGPT自身が、真偽や倫理性を判断できないこと
- 2021年までの情報しか学習していないこと
倫理的に不適切な文章が生成される
ChatGPTを利用する際、生成されたデータに倫理的に不適切な表現が含まれるリスクがあります。これは、ChatGPTがインターネット上のデータから学習しているため、真偽や倫理性を判断できないことが原因です。
社員がChatGPTに依存してしまう
ChatGPTを業務に導入することで、社員がChatGPTに頼りすぎてしまうリスクがあります。
ChatGPTは大変便利なツールであり、
- メールの作成
- 文章コンテンツの自動生成
- 企業や市場調査
- 企画立案
など、ビジネスのあらゆるシーンで活用できます。
一方で、社員がChatGPTを頼りすぎてしまうと次のようなことに繋がるのではないでしょうか?
- 創造力や批判的思考力の低下
- コミュニケーション能力の低下
- 学習意欲の減退
- 間違った判断や個性喪失、コンテンツの平凡化
悪意のあるプラグインによる情報漏洩
ChatGPTを外部サービスと連携することでより便利な使い方ができ、その際に利用するプラグインにもリスクがあります。正常に見えるプラグインでも、攻撃者はユーザを欺き悪意のあるプラグインをインストールさせ、個人情報や機密情報を入力してしまうと、瞬時に拡散されてしまう可能性があります。プラグインをインストールする際は注意しなければいけません。
ChatGPTを企業利用するリスクへの対策6選
リスクへの対策は以下の6つです。
- 情報漏洩への対策
- 著作権侵害やプライバシー侵害への対策
- 虚偽情報の生成への対策
- 倫理的に不適切な文章が生成されることへの対策
- 社員がChatGPTに依存してしまうことへの対策
- 悪意のあるプラグインによるセキュリティ対策
それぞれを解説します。
情報漏洩への対策
情報漏洩対策として有効なのは、以下の2つです。
- 重要データを入力しない
- ChatGPT APIを利用する
1つ目について、情報漏洩を防ぐ最も手っ取り早い方法は「重要データを入力しない」ことです。とはいえ、業務でChatGPTをフル活用したい場合、入力できるデータに制限があるのは不便ですよね?
そこで2つ目におすすめの対策が、「ChatGPT APIを利用する」です。OpenAI社によると、API経由のデータは学習には利用されず、情報漏洩のリスクを低減できます。
ただし、APIを経由する場合は、次の2点を考える必要があります。
- APIの利用料
- APIを利用するためのシステムや機能の考慮
まずは、APIの利用料について。これは、入力した文字数に応じて決まります。(下表参照)
| GPT-4 Turbo | GPT-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| モデル | gpt-4-1106-preview | gpt-4-1106-vision-preview | gpt-4 | gpt-4-32k |
| 入力(1,000トークンあたり) | 0.01ドル | 0.01ドル | 0.03ドル | 0.06ドル |
| 出力(1,000トークンあたり) | 0.03ドル | 0.03ドル | 0.06ドル | 0.12ドル |
※日本語の場合、ひらがな1文字=1トークン/漢字1文字=2~3トークン
次に、システムや機能の考慮について。ChatGPT APIを利用するためには、社内システムへどう連携するか考える必要があります。例えば、Slack というチャットツールに、ChatGPT APIを利用したChatBotを組み込んでいます。
社内での連絡ツールとしてSlackを使用している場合だと、ChatGPT APIとSlackを連携してチャットボットを作成するのがいいでしょう。ChatGPT APIを導入する際は、利用料金や工数などのバランスを考えるようにしましょう。
著作権侵害やプライバシー侵害への対策
著作権侵害やプライバシー侵害しないための対策は、次の3点です。
- 社内ルールと確認プロセスの整備
- 法律や規則の理解・遵守
- 著作権やプライバシー保護の研修・教育プログラム
1. 社内ルールと確認プロセスの整備
倫理的リスクと同様に、生成データ利用に関する社内規約やルールを策定し、確認プロセスを整備することが重要です。
また、万一問題のあるデータが含まれる場合に、そのデータを改善するプロセスを構築しましょう。
2. 法律や規則の理解・遵守
著作権やプライバシーに関する法律や規制を理解し、遵守することが不可欠です。特に、国や地域によって著作権法やデータ保護法が異なるため、対象市場や顧客の法的要件を把握することが重要です。
3. 著作権やプライバシー保護の研修・教育プログラム
従業員や関係者に対して、著作権やプライバシー保護に関する研修や教育プログラムを実施し、リテラシーを高めましょう。こうすることで、企業・組織はChatGPTを適切かつ安全に活用できます。
虚偽情報の生成への対策
対策としては、次のことが考えられます。
- 回答を100%鵜呑みにしない:ChatGPTが誤った情報を出力する可能性がある旨を念頭におく
- 社内ルールを定める:ChatGPTの回答結果をどのように利用するか、社内でルールを決める
- 確認プロセスの整備:ChatGPTの回答結果の真偽をどのように確認するか、社内でプロセスを整備する
上記の他にも、社内での定期的な情報共有を行うことが、リスク低減に繋がります。
倫理的に不適切な文章が生成されることへの対策
倫理的に不適切な文章が生成されることへの対策としては、次のことが考えられます
- 社内ルールの制定:ChatGPTが生成したデータをどのように利用するか、社内ルールを定める
- 確認プロセスの確立:ChatGPTの回答結果が本当に正しいのか、常にチェックする
- 改善プロセスの確立:万一ChatGPTが問題のある回答を出力した場合、どう改善するかを決めておく
上記の対策により、倫理的リスクを低減しながら、効果的にChatGPTを利用できるでしょう。
一方で、社内体制や規約を厳しくしすぎると、ChatGPTの利用に多大なコストがかかってしまうこともあります。利用目的や重要度に応じて規約や利用方法を考え、適切なバランスを取るよう心掛けましょうね。
社員がChatGPTに依存してしまうことへの対策
社員がChatGPTに依存してしまうことへの対策として、次のようなものが考えられます。
- 役割の明確化:ChatGPTと人間それぞれが担うべきタスクを明確に区別する
- 利用制限:ChatGPTを利用できるタスクや時間を制限する
- 評価基準の設定:独自の思考や分析が加えられた成果物を高く評価する
いくらChatGPTが便利だとはいえ、最終的な意思決定や創造的なタスクは人間が担う必要があります。上記の対策を実施することで、ChatGPTに依存することなく、より効果的に活用できるようになるでしょう。
悪意のあるプラグインによるセキュリティ対策
悪意のあるプラグインによる攻撃を防ぐ方法としては、次のようなものが考えられます。
- ChatGPTの最新バージョンを利用:最新版のChatGPTを利用することで脆弱性に対応しやすくなります。
- 信頼できるソースからのみプラグインのインストール:悪意のあるプラグインをインストールしないためにも、信頼できるソースからのみ利用するようにしましょう。
- URLの検証:信頼できるURLかどうか確認し、怪しいものは避ける。
ChatGPTと外部サービスを連携させることでより便利な使い方ができますが、上記の対策を講じながら利用するようにしましょう。
セキュリティリスクが発生してからでは手遅れになってしまう可能性があります。安全にChatGPTを使うためにも常に適切な対策を行うことをおすすめします。
なお、ChatGPTを法人利用する方法について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

ChatGPTを業務に利用している企業事例5選
前の章でChatGPTのリスクについて詳しく説明しました。
ビジネスの現場では、これらのリスクを認識しながらも、AIの恩恵を活かすために、具体的な対策を講じてChatGPTを活用している企業が存在します。
- 【サイバーエージェント】ChatGPTでコニュニケーション工数を削減
- 【パナソニックホールディングス】AI技術で生産性向上
- 【農林水産省】AIの力で精度の高いマニュアル作成
- 【伊藤忠商事】チャットとChatGPTの連携
- 【三井化学】AI技術で新規用途発見のスピード向上
ここでは、5つの企業に焦点を当て、どのようにChatGPTを取り入れ、そしてリスクにどのように対処しているのかを紹介します。
【サイバーエージェント】ChatGPTでコニュニケーション工数を削減
サイバーエージェントでは「ChatGPTオペレーション変革室」を設立し、ChatGPTをデジタル広告のオペレーションに活用しています。サイバーエージェントではこれまで、広告オペレーションに月間約23万時間もの時間を費やしていました。
この莫大な作業時間を削減するために、同社では
- 自動回答
- 海外拠点との意思疎通
などの社内コミュニケーションにChatGPTを導入し、作業時間の30%(約7時間)削減を目指しています。
また同社ではOpenAIの規約に従い、API連携を利用し、顧客情報を含まない形で運用を行っているのだとか。
これにより、最新の動向とリスク対応策を踏まえ、安全にChatGPTを活用しているそうです。*2
【パナソニックホールディングス】AI技術で生産性向上
パナソニックでは、AIアシスタントサービス「PX-GPT」を全社員に展開し、国内社員約9万人が本格的に利用を開始しました。
PX-GPTは、パナソニック コネクトが活用している「ConnectGPT」をベースに開発したもので、「Panasonic Transformation(PX)」というプロジェクトの一環として導入されました。
PX-GPTは、MicrosoftのパブリッククラウドMicrosoft Azure上で利用できるAzure OpenAI Serviceを活用しており、社内イントラネットからアクセス可能です。
またセキュリティ面に配慮し、入力情報は一定期間を過ぎたら消去され、二次利用や第三者提供はされないように設計されているのだとか。
パナソニックは、このサービスを通じて、社員の生産性向上と業務プロセスの進化を促進し、新たなビジネスアイデアの創出を目指しています。*3
【農林水産省】AIの力で精度の高いマニュアル作成
農林水産省では、2023年4月に一部の業務でChatGPTを導入することを発表しました。
現在既に導入されているかは定かではありませんが、4月時点で使用を想定していた作業は「農林水産省共通申請サービス(eMAFF)」の利用者向けのマニュアル改定です。
マニュアル改訂は正確性が求められるため、文章作成や適切に修正するといった作業にChatGPTを使うとのことです。*4
【伊藤忠商事】チャットとChatGPTの連携
伊藤忠商事では、社内版ChatGPTを開発し、全社員である4,200人に導入を開始しました。
繊維、機械、金融、エネルギー、化学品など幅広い分野で事業を展開している総合商社である伊藤忠商事は、ChatGPTが業務の生産性向上につながるか確認するために生成AIの導入を決めました。
議事録作成や文章の要約、一部の調査業務での利用が中心となり、伊藤忠社内で使われているビジネスチャットとAPI連携して、慣れ親しんだUIで使えるようにしたそうです。*5
【三井化学】AI技術で新規用途発見のスピード向上
2023年4月に三井化学と日本アイ・ビー・エムが既存の化学製品の新規用途発見スピードを爆速化するためにChatGPTを活用し始めました。従来では三井化学の20以上の事業部門がIBMのAIを使って100以上の新規用途を発見し一定の成果を上げていましたが、時間がかかりすぎている課題がありました。
時間短縮のため、特許やニュース、SNS、交流サイトなどテキストデータから新規用途の候補を生成することで、爆速化する見通しです。*6
なお、ChatGPTの活用事例について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。
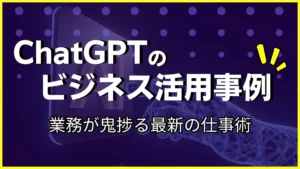
ChatGPTを活用したプログラミングやアイデア出し、業務活用事例まで、さまざまなトピックを取り揃えております。
続きを読む
ChatGPTを企業利用する上での注意点
ここまで、ChatGPTの主要なリスクとそれに対応してAIを活用した実際の企業例を挙げてきました。
ここからはChatGPTを企業利用する際に注意しておくべき点を解説します。
2021年までの情報しか提供できない
ChatGPTの学習モデルは2023年4月までになっており、最新のデータにアクセスできない点は注意が必要です。(ChatGPT無料版の場合は、2021年9月まで)
特にリサーチ業務や市場調査でChatGPTを利用する場合は、データが取得できなかったり古いデータを参照してしまう可能性があるので利用にあたっては精査が必要です。
例えば2023年の日本のGDPを訪ねた場合、正式な数値が発表されていないとされます。
もし最新情報を仕入れたい場合は、BingAIなど、ブラウジング機能を持ったAIツールを使うのも手です。
出力言語を指定できない
ChatGPTは入力したワードに応じて自動的に言語を判別する為、入力した言語と違う言語で出力される場合もあります。翻訳を頼めば翻訳してくれますが、プロンプトで「日本語でお願いします」などと入力する必要があります。
日本語と英語での情報量の違い
ChatGPTでは、日本語と英語で情報量に差がある場合があります。ChatGPT側のアップデートでその差は縮まっていますが、日本語で思ったような回答が得られない場合は、英語で入力すると最適な回答が得られるかもしれません。
アップデートによって機能や精度が変わる可能性がある
ChatGPT はまだまだ発展途上のサービスで、同サービスは短い期間でどんどん新しい機能や精度の改善、安定の向上など様々なアップデートが加えられています。基本的にアップデートはユーザーにとって大きなメリットですが、ChatGPTのハック的な使い方やより良い質問方法なども変化する可能性があります。ChatGPTを最大限活用したい場合は、リリースノートを常に確認しておきましょう。*7
長文を入力できない
入力しようとしたら、このようなエラーが出たことはないでしょうか?
これは、トークン数オーバー(制限文字数オーバーのようなもの)が関係します。
ChatGPTの入出力の長さは、”トークン数”という単位で決められています。
例えば、GPT-4では1回の入出力あたり最大8000トークンまで。
文字数にするとどうなるか気になると思いますが、言語によって換算方法が違うんです。
大雑把ですが、英語と日本語では次のようになります。
- 英語:1単語=1トークン
- 日本語:ひらがな1文字=1トークン/漢字1文字=2~3トークン
上記からもわかるように、日本語よりも英語の方が多くの情報を入力できます。
日本語で長文が入力できないときは、英語に翻訳して入力しましょう。
翻訳するときは、DeepL(https://www.deepl.com/translator) がおすすめです。
まずは、このように翻訳しましょう。(例なので、短文ではありますが……)
そして、翻訳結果をChatGPTに貼り付け、実行しましょう。
なお、AIを用いた翻訳について知りたい方はこちらをご覧ください。

ChatGPTのリスクを知った上で企業利用しよう!
ChatGPTを企業利用する上でのリスク・注意点、およびその対策は下記のとおりです。
| リスク・注意点 | 対策 |
|---|---|
| 情報漏洩 | ・重要データを入力しない・ChatGPTのAPIを利用する |
| 著作権侵害やプライバシー侵害 | ・社内ルールと確認プロセスの整備・法律や規則の理解・遵守・著作権やプライバシー保護の研修・教育プログラム |
| 虚偽情報の生成 | ・回答を100%鵜呑みにしない・回答結果を利用する際の社内ルールを決める・回答結果の確認プロセスを整備する |
| 倫理的に不適切な文章を生成 | ・生成されたデータの利用に関する社内ルールを作る・確認プロセスを確立して常にチェックする・万一問題のある回答が出力された場合の改善方法を決める |
| 社員のChatGPTへの依存 | ・AIが生成するコンテンツと人間の専門知識のバランスを保つ・人間の判断と直感の価値を維持する・ビジネスプロセスにおけるAIの役割を定期的に見直し、評価する・人間の努力を補完するように、人間とChatGPTの役割を明確化する |
| 悪意のあるプラグインによるアカウント侵害 | ・ChatGPTの最新バージョンを利用・信頼できるソースからのみプラグインのインストール・URLの検証 |
| 最新情報へアクセスできない(2023年4月まで) | BingAIなど、ブラウジング機能を持つツールを使う |
| 出力言語を指定できない | プロンプトで言語を指定する |
| 日本語と英語での情報量に差がある | 英語で入力する |
| アップデートによって機能や精度が変わる | リリースノートをこまめに確認する |
| 長文が入力できない | 英語で入力する |
ChatGPTは非常に便利なツールであり、企業利用することで間違いなく業務効率は飛躍的に向上します。
今回紹介したリスクとその対策を忘れることなく、誠実かつ効果的な利用方法を見つけ出すことが、今後の企業にとって重要となるでしょう。
- *1:Don’t Chat With ChatGPT: Amazon’s Warning To Employees
- *2:ChatGPTで広告運用の実行スピードを大幅短縮する「ChatGPTオペレーション変革室」を設立
- *3:AIアシスタントサービス「PX-GPT」をパナソニックグループ全社員へ拡大 国内約9万人が本格利用開始
- *4:数千ページのマニュアル改訂「ChatGPT」活用へ 農林水産省
- *5:伊藤忠商事が「社内版ChatGPT」を4200人に導入開始…“商社が使う生成AI”への期待
- *6:三井化学は「新規開発」がChatGPTで爆速に!化学業界の現場で使えるプロンプトを特別公開
- *7:ChatGPT — Release Notes
最後に
いかがだったでしょうか?
GPT-3.5 Turboの最新アップデートで、より高速かつ低コストでのAI活用が可能になりました。自社での導入・活用を検討する際に、最適なモデル選定や活用方法について、一緒に考えてみませんか?
弊社では
・マーケティングやエンジニアリングなどの専門知識を学習させたAI社員の開発
・要件定義・業務フロー作成を80%自動化できる自律型AIエージェントの開発
・生成AIとRPAを組み合わせた業務自動化ツールの開発
・社内人事業務を99%自動化できるAIツールの開発
・ハルシネーション対策AIツールの開発
・自社専用のAIチャットボットの開発
などの開発実績がございます。
まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。
➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。
セミナー内容や料金については、ご相談ください。
また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。