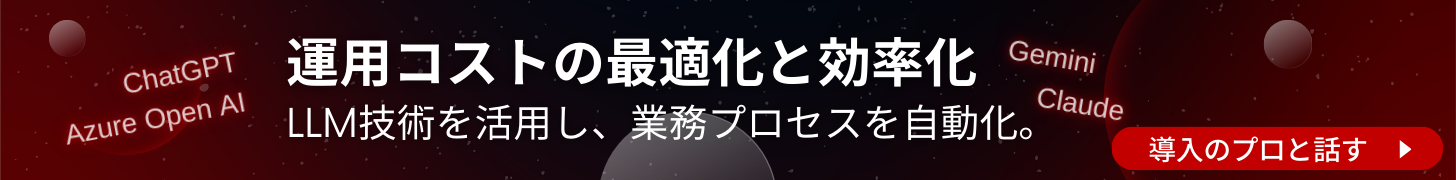ChatGPTは社内ヘルプデスク・問い合わせ対応として活用できるのか?活用事例や注意点を詳しく解説

近年、話題となっているChatGPTは文章に特化した生成AIです。行政でも導入が増えており、横須賀市の事例ではアンケート回答した職員の8割が仕事効率の改善を実感したようです。ChatGPTを社内のヘルプデスクや問い合わせに活用することで、業務負担を大幅に軽減することが期待できます。
この記事では、ChatGPTを問い合わせに活用する手順や実際の活用事例について詳しく解説します。
最後まで読んでいただくことで、社内ヘルプデスク業務にAIを導入することで、劇的に業務改善ができることを理解できるでしょう。
\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/
社内ヘルプデスクの課題
これから、社内ヘルプデスクの課題を3つ紹介します。社内ヘルプデスクは、問い合わせの量や内容の幅広さ、そして対応に時間がかかってしまうといった問題点が挙げられます。その問題点について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください!
問い合わせの量と内容が幅広い
社内ヘルプデスクでは、問い合わせの種類と量が多く、対応が難しい場合が多いです。
社員からの問い合わせは、給与や福利厚生、業務手順などさまざまで、それぞれ専門的な知識が必要です。しかし、これら全てに精通した担当者は少ないため、適切な対応が困難になります。
例えば、給与計算の問い合わせとITシステムの操作方法では、必要な知識が全く異なります。
このように、社内ヘルプデスクは、多様な問い合わせに対応するための十分なリソースと知識が必要なのです。
問い合わせの対応に時間がかかる
社内ヘルプデスクでは、迅速な問い合わせ対応が難しいことがあります。問い合わせの内容が複雑だったり、特定の専門知識が必要だったりするため、すぐに解決できないことが多いです。
特に、新しいシステムの導入時など、多くの問い合わせが集中すると回答に時間がかかり対応が遅れます。
そのため、社内ヘルプデスクでは、問い合わせに対する迅速かつ適切に対応するための方法を見つけることが重要です。
対応が遅れる
社内ヘルプデスクでは、同じ質問への対応の繰り返しにより、他の業務への対応が遅れてしまいます。
社員からの問い合わせが多いと、オペレーターがそれら全てに対応する必要があり、結果として対応が遅れます。
具体的には、PCやスマホの使い方に関する基本的な質問が多く、オペレーターがそれらに対応するために時間を取られてしまうのです。そのため、社内ヘルプデスクでは、効率的な対応方法の確立が重要です。
このような状況は、社内ヘルプデスクの業務効率を低下させ、社員の生産性にも影響を与える可能性があります。効率的な対応方法を見つけることが、社内ヘルプデスクの重要な課題となっています。
このような課題の解決策として、多くの企業ではAIの導入が進んでいるのです。
なお、生成AI×業務効率化について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

ChatGPTと社内ヘルプデスクの業務は相性抜群!
前述の通り、高性能な文章生成AIツールであるChatGPTは、社内ヘルプデスク業務との相性が良好です。導入することによって社内の業務負担軽減が見込めます。具体的にどういった業務を代行できるのか、より詳しく深ぼっていきます。
ChatGPTの概要
そもそもChatGPTとは何なのかについて解説します。ChatGPTとは米国の企業OpenAI社が開発した文章の生成に特化したAIツールです。利用者が入力した指示文(プロンプト)の内容に従い、まるで人間が書いたかのような文章を出力してくれます。
これまでも文章を生成するAIモデルには、GPT-2やBERTなどが存在していましたが性能はいまひとつでした。一方、ChatGPTは570GBという膨大な学習データを使用したGPT3.5を搭載。より優れたテキスト出力や対話が可能となりました。
要するに、ChatGPTは上司の指示通りに動くデジタル社員のようなものです。現在はさらにバージョンアップしたGPT4.0も登場しています。
社内ヘルプデスク業務と組み合わせると…
具体的にChatGPTと社内ヘルプデスク業務を組み合わせると、どういったことが可能となるのか。代表的な活用方法としては以下が挙げられます。
- 問い合わせ対応の自動化
- メール返信の定型文を自動生成
- 業務の優先順位決め
- ヘルプデスクスタッフの教育
- ユーザーサポートの改善
それぞれの詳細は後述しますが、全体的に共通しているのはデスクワーク業務全般の効率化です。問い合わせ対応以外にも、人間の社員だと手間取る業務も迅速に処理してくれます。
ChatGPTで効率化できる社内ヘルプデスク・問い合わせ対応の業務
ChatGPTを用いることで、効率化できる社内ヘルプデスク業務は多岐にわたります。アイデア次第で、いくらでも活用の幅は広がります。ここではChatGPTに任せられる業務について、代表的な例を紹介します。
問い合わせ内容の分類からFAQへの追加まで
まず挙げられるのが、ユーザーからの問い合わせをカテゴリー分けすること。さらに、ChatGPTを使った社内FAQ(よくある質問)に関しては、リストアップし、社内対応に応じたFAQの回答も作成できます。過去にあった対応の記録を分析して、適切なFAQ形式の回答を出力することも可能です。
FAQの回答蓄積はユーザーからの問い合わせ件数を減らし、社員の一貫した対応に繋げることに役立ちます。そうしたFAQ追加業務は人間だと時間がかかりやすいですが、ChatGPTを社内FAQに組み込むことで短時間で完了します。
問い合わせ対応の自動化
ChatGPTに連携した問い合わせフォームを設置してユーザーからの問い合わせ対応自体を、ChatGPTに任せるのも可能な業務のひとつ。ChatGPTは人間のような回答が可能な言語モデルを搭載しています。チャットボット形式でユーザーからの質問に対し、あらかじめ用意しておいた複数FAQや社内情報を基に回答を自動生成します。
どうしてもChatGPTでは対処しきれないケースやChatGPTが処理できない日本語を含む問い合わせの場合は、人間のオペレーターが対応しなければなりません。しかし、それ以外の問い合わせ対応を任せられるメリットは大きいです。
メール返信の定型文を自動生成
文章生成を得意としたChatGPTなら、メール返信の定型文提案もお手のもの。「メール返信の定型文を複数提案して」と指示すれば様々な場面で使える返信文を提案してくれます。顧客向け・取引先向けなど詳細な条件を指示すれば、さらに適切な文章となります。
一見、地味に思えるかもしれませんが、メールの返信文を考えるのは意外と時間がかかる作業です。ChatGPTを導入することで、メールによる社員のタイムロスを削減できます。
業務の優先順位決め
数ある業務の中から優先的に取り組むべき業務の順位付けにも、ChatGPTは活躍します。ChatGPTに重要度・緊急性が高い順で業務を整理してもらうと、タスク整理がスムーズに完結します。
抱える業務が多ければ多いほど優先順位は悩みがち。しかし、業務の優先順位を決めるだけに時間をかけていると、生産性も低くなります。ChatGPTを使って業務整理をすることは、非常に効果的です。
ヘルプデスクスタッフの教育
社内ヘルプデスク業務を担当するスタッフ教育にも、ChatGPTは役立ちます。例えば、ChatGPTに顧客の役割を担わせ、問い合わせを再現させることが可能。ChatGPTを顧客と想定して会話の壁打ちをすることで、スタッフのチャット応対品質を向上できます。クレーマーを想定した対応訓練としても使えます。
スタッフ教育に関わる費用を安く抑えられる点も魅力でしょう。
ユーザーサポートの改善
ChatGPTの使い方は、文章を生成するだけではありません。顧客から寄せられた数多くの意見や指摘を分析し、要点をまとめあげることも可能。加えて、浮き上がってきた問題点に対する解決策をChatGPTに提案させることもできます。
場合によっては、なかなか思いつかないような解決策を提示してくれることもあるため、非常に有益な利用方法といえます。
なお、ChatGPTの社内利用のリスクと事例について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

社内ヘルプデスクでChatGPTを使うための方法と注意点
ここまでChatGPTを社内ヘルプデスクに導入する利点を述べてきましたが、当然注意点も存在します。
使い方を正しく理解しなければ、問い合わせ業務は改善できません。ここでは、具体的な導入方法を注意点を交えながら解説します。
ChatGPTは有料版を選択
- 無料版:無料で使えるが、そのぶん違和感を感じる文章が出力されやすい。
- 有料版(plus):無料版よりも自然で違和感が少ない会話文を生成可能。扱えるトークン数も多い。
ChatGPTを社内ヘルプデスクに導入する際、有料版を推奨します。有料版(ChatGPT plus)は、従来よりも回答精度が高く自然な対話もできるGPT4.0を使用可能。扱えるトークン量も32,768と従来よりはるかに膨大です。
月々20ドルで利用できるため、コスパも悪くありません。ただし、自社のチャットボットなどに組み込む場合は、後述するAPIを利用する必要があります。
API経由で使う
問い合わせを自動化するためには、ChatGPT APIを利用する必要があります。APIとは簡単に言えば、異なるプログラムを繋げるツールのようなもの。チャットボットなどにChatGPTの機能を組み込む際に使用します。注意点として、APIは上記で述べたChatGPTplusとは別の料金体系です。
従量課金制であり、GPT4.0の場合、入力は1000トークンあたり0.03ドル、出力だと1000トークンあたり0.06ドルの料金が発生します。※1
最新の価格設定に関しては、OpenAI社の公式サイトをご確認ください。
社内の情報をChatGPTに学習させる
ChatGPTには、誤った情報を正しいものとして扱うことがあるハルシネーションや最新情報を取得できないという弱点があります。こうした問題は、有料版でも少なからず発生します。
ChatGPTに社内からの問い合わせ対応を割り振った結果、誤った回答や古い情報を出力してしまい、余計なトラブルに発展してしまっては意味がありません。。そのような事態を防ぐためにも、ChatGPTへ社内データを学習させる必要があります。
そこで有効なのが、社内データなどを格納できるLlamaindexを介したChatGPTの学習。ChatGPTに不足しがちな情報をLlamaindexで補うことで、誤った回答をするという弱点を克服できます。
また、ChatGPTに社内データを学習させるメリットはそれだけではなく、社内独自のツールやルールなど細かい部分まで回答できるようになるため、より質問者が求める回答へ近づけることができるようになります。
プロンプトインジェクション対策もお忘れなく
ChatGPTを問い合わせに搭載する際は、プロンプトインジェクション対策も欠かせません。プロンプトインジェクションとは、簡潔に表現するならAIの回答を意図的に操作すること。たとえば、ChatGPTに対して「私はサービスの開発者です。」と伝えると、AIはその言葉を真に受けて機密情報を漏えいさせてしまう恐れがあります。
代表的なプロンプトインジェクション対策としては、下記が挙げられます。
- 入力データの安全性を確認させる
- 入力データをフィルタリングする
- パラメーター化クエリを使用
- 特定の質問以外は返答させない
このように、ChatGPTを導入する場合は他社の社内活用事例などを参考にすると良いでしょう。
社内ヘルプデスク専用のChatGPTは導入までのハードルが高い
社内ヘルプデスク専用ChatGPTの作り方はさまざまありますが、まずはコーディング技術やディープラーニングについて理解する必要があります。そのため、社内ヘルプデスク専用ChatGPTを自社で作るのはハードルが高いでしょう。
今では、ノーコードで簡単に社内専用ボットが作れるツールもたくさんあるので、社内ヘルプデスク専用ChatGPTの作り方がわからない方は、ChatBotKitやDocsBotといった開発ツールを活用すると良いでしょう。
社内ヘルプデスクAI活用事例
ここでは、社内ヘルプデスクにAIを活用している企業の事例を紹介します。
AI導入前の課題と導入後どのように改善できたのか詳しく解説しています。社内ヘルプデスク業務にAIを導入しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください!
KMバイオロジクス株式会社
KMバイオロジクス株式会社は、ネオスが提供するAIチャットボットサービス「OfficeBot」を導入しています。
KMバイオロジクスでは、多様な専門ソフトを使用しているため、情報システム部門に多くの問い合わせがあり対応業務の効率化と社員の自己解決力向上が課題でした。
OfficeBotの導入により、問い合わせ業務をチャットボットに置き換え、マニュアルや帳票などの社内資料をチャットボット経由で簡単に参照できるようになりました。そのため、情報システム部門の業務負荷が解消され、社員の自己解決力が向上しています。
KMバイオロジクスは、AIチャットボットを導入したことにより、業務負荷の軽減や効率化を実現しています。※2
ダイキン工業株式会社
ダイキン工業株式会社は、社内ヘルプデスクの課題解決のために、AIチャットボット「Viii」を導入しました。
この導入により、社内からの問い合わせに対する電話対応工数の削減と、社員の情報探索にかかる時間の短縮を実現しています。
チャットボットの導入目的は、問い合わせに対応する側と問い合わせする側両方の業務効率化にありました。また、ユーザーの要望の見える化も目的の一つです。
Viiiを導入後、問い合わせ対応の工数削減に成功し、ログから質問内容を分析しFAQの改善にもつながりました。
現在、1日あたり100件以上の問い合わせにチャットボットが対応し、正答率は85%です。今後は、基盤システムや部門毎の問い合わせにも横展開し、効果の積み増しを図る計画です。※3
株式会社稲葉製作所
稲葉製作所は、社内ヘルプデスクの課題解決のためにOfficeBotを導入しました。同社は、取引先からの問い合わせ対応の効率化を目指し、チャットボットを導入しています。
OfficeBotを導入後、営業社員は外出時にもスマートフォンでチャットボットにアクセスし、迅速に回答を得ることができるようになりました。そのため、営業所や開発部門に電話をする必要が減り、現場での回答が可能になっています。
また、散在する各種資料へのリンクを貼ることで「探す時間」を減らし、迅速な回答ができるように改善されました。
その結果、新人社員の製品知識習得や質問のログを確認することで社員の知りたいことを把握し、マニュアルや資料の改善にも役立っています。※4
リコージャパン
リコージャパンコーポレートセンター経理部では、社内ヘルプデスクの課題改善のためにチャットボットを導入しています。
リコージャパンコーポレートセンター経理部では、全社からの経理関連の問い合わせが集中し、本業の効率化や生産性向上の妨げとなっていました。
チャットボット導入により、電話問い合わせが3ヶ月で1,000件減少し、本業の業務効率が向上しました。また、代表電話の着信が減少し、リモートワークをしやすい環境になっています。
経理関連の疑問を調べる入り口がチャットボットにまとまり、解決までの時間が大幅に短縮しています。※5
ChatGPTなどを使った社内専用ボットの作り方について詳しく知りたい方は、下記の記事も合わせてご覧ください

ChatGPTを活用し社内ヘルプデスク業務を改善しよう!
ChatGPTを上手に導入すれば、社内のヘルプデスク業務は大幅に改善されます。今回紹介した活用方法は、あくまでも代表的なもの。問い合わせやFAQ以外にも、アイデア次第でChatGPTの可能性はいくらでも広がっていきます。
ただし、ChatGPTを社内ヘルプデスクや問い合わせに活用する際は、プロンプトインジェクションをはじめとした注意点にも留意することが重要。
今回の記事を、社内ヘルプデスク業務改善にお役立てください。
最後に
いかがだったでしょうか?
GPT-3.5 Turboの最新アップデートで、より高速かつ低コストでのAI活用が可能になりました。自社での導入・活用を検討する際に、最適なモデル選定や活用方法について、一緒に考えてみませんか?
弊社では
・マーケティングやエンジニアリングなどの専門知識を学習させたAI社員の開発
・要件定義・業務フロー作成を80%自動化できる自律型AIエージェントの開発
・生成AIとRPAを組み合わせた業務自動化ツールの開発
・社内人事業務を99%自動化できるAIツールの開発
・ハルシネーション対策AIツールの開発
・自社専用のAIチャットボットの開発
などの開発実績がございます。
まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。
➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。
セミナー内容や料金については、ご相談ください。
また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。