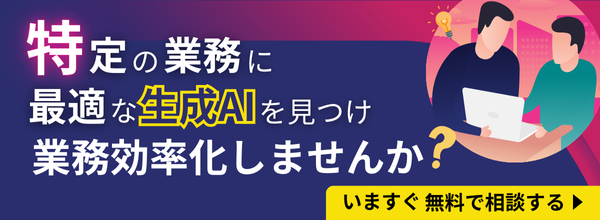リサーチ業務に革新をもたらす生成AIの活用法とは?おすすめツールと注意点も解説
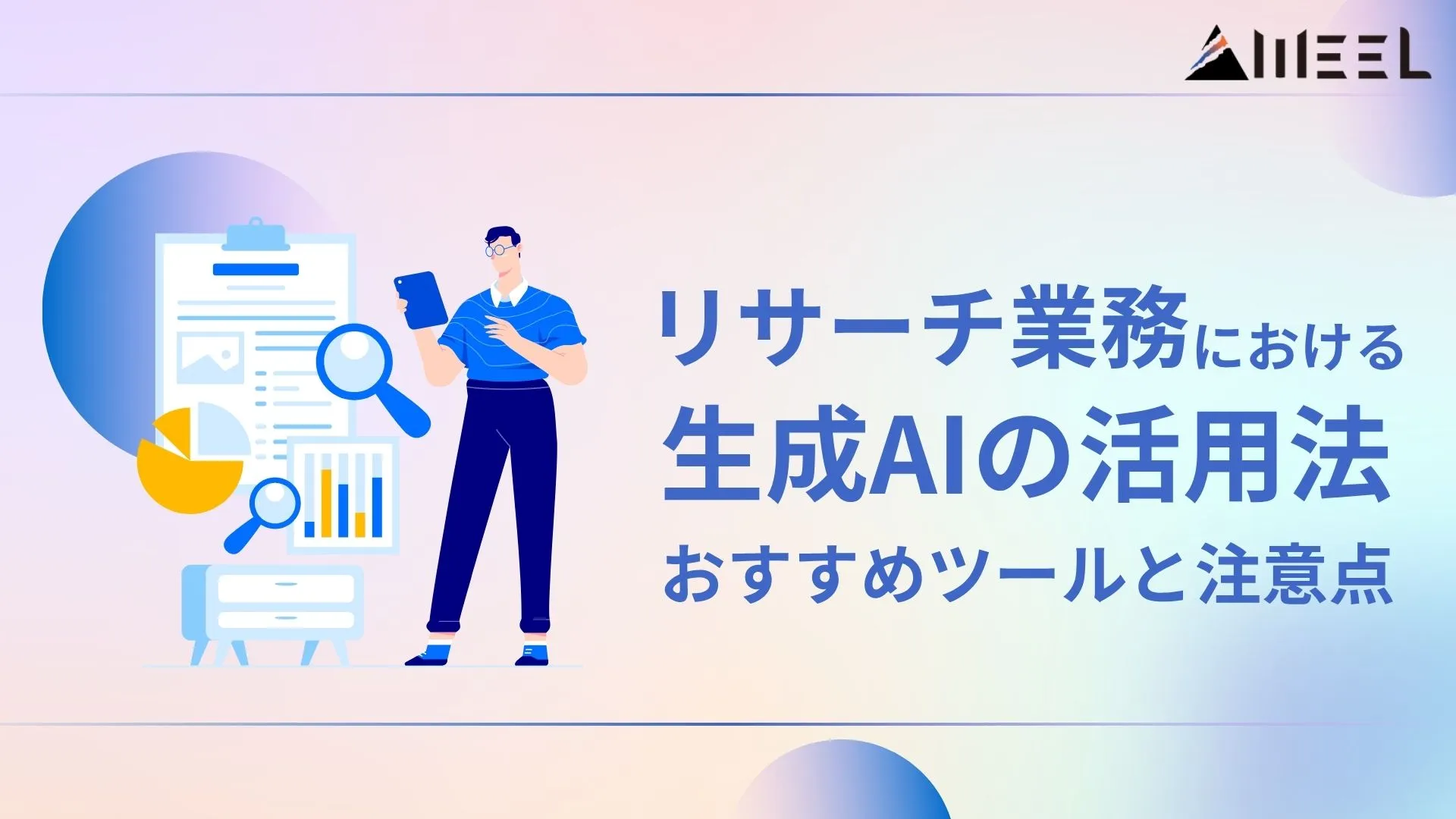
忙しいビジネスパーソンにとって、もはや日常的なタスクともいえるのが、情報収集や分析などのリサーチ業務です。その一部を生成AIに任せることで、これまで時間と手間がかかっていた作業が劇的に効率化できるようになりました。
とはいえ「どんなツールを使えばよいの?」「精度や信頼性、セキュリティ面の問題は?」など、様々な疑問を抱く方も多いはず。本記事では、生成AIがどのようにリサーチ業務に貢献するのかを、具体例とともにわかりやすく解説します。
最後まで読めば、あなたも明日から生成AIを活用したリサーチのスペシャリストとして、職場でも一目置かれる存在になること間違いなし!
ぜひ、できることからどんどん実践してみてくださいね。
\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/
リサーチ業務×生成AIの概要

生成AIは、大量の情報から必要なデータを抽出し、ユーザーのニーズに合わせた分析や要約、整理することが得意です。これにより従来の検索や人力による調査に比べ、スピードや網羅性、柔軟性が格段に向上しています。
また業務に応じて様々なAIツールを使い分けることで、業務の初期段階から分析フェーズまで幅広くサポートすることも可能なため、これからのビジネスユーザーには必須のツールと言えるでしょう。
なお、生成AI時代の人材育成について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

リサーチ業務で生成AIができること
生成AIは、これまでの検索ツールのように、単にWeb上にある情報へアクセスするだけでなく、様々なタスクの実行が可能です。必要に応じて業務の様々な場面で使いこなすことにより、生産性が飛躍的に向上します!
的を絞ったリサーチ
従来の検索エンジンでは、特定の業界や分野を深掘りしてリサーチする場合、ある程度の前提知識が必要で、なおかつ何度も検索ワードを組み合わせながら、ようやく必要な情報にたどり着くのが当たり前でした。
しかし生成AIを活用すると、プロンプトを工夫すれば、特定の業界や専門知識、技術、各種事例などに関する情報を素早く収集することが可能です。
特にToB営業やコンサルタントなど、その業界に詳しくない場合でも、時間をかけずに専門的な業界の情報収集や要点の整理やまとめ、市場調査などを瞬時に行うことができます。
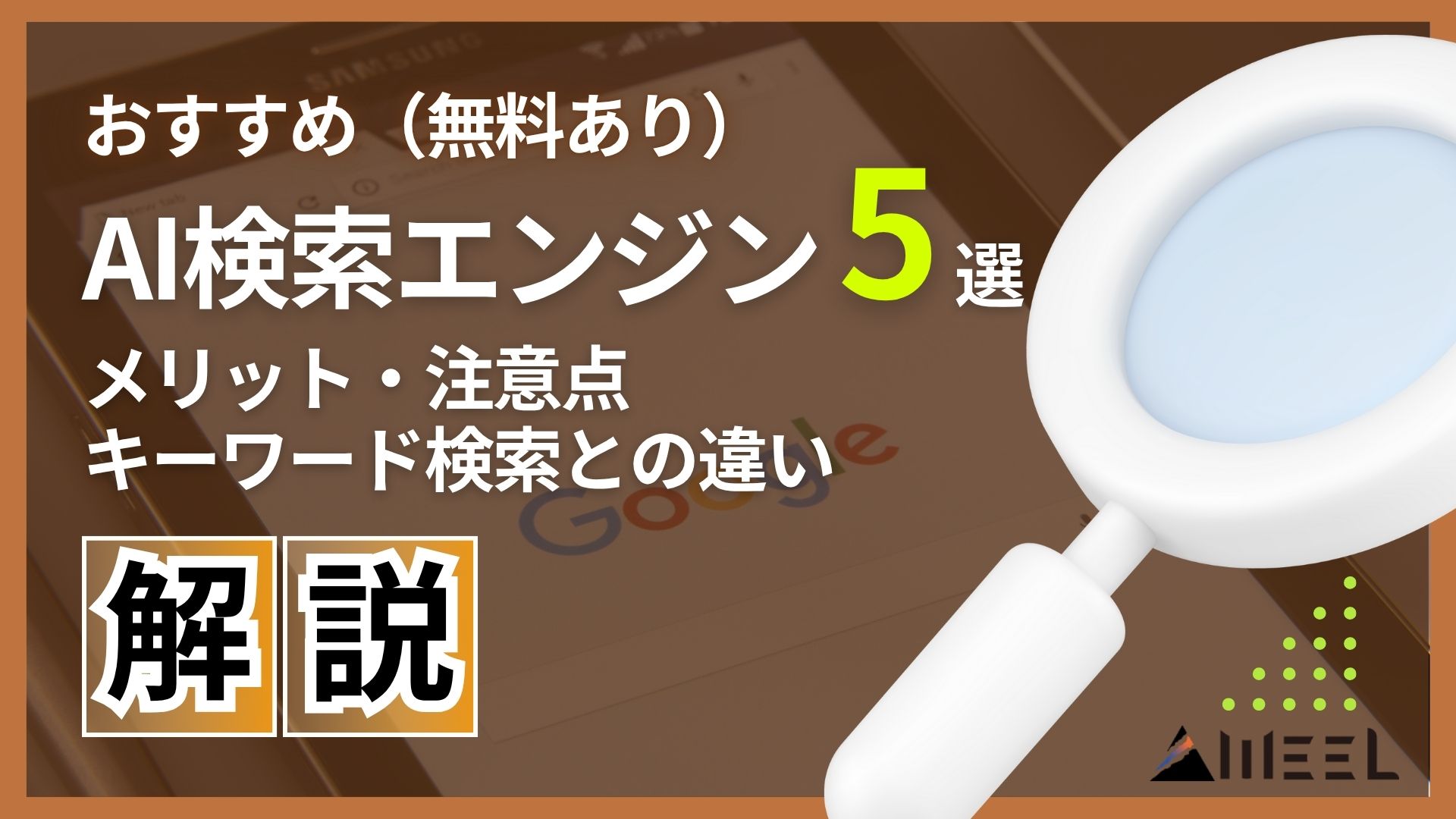
手書き・画像媒体への対応
生成AIはOCR(光学文字認識)機能や画像解析モデルと連携することで、紙の資料やホワイトボード、手書きのメモなどを画像から文字情報に変換できます。
これにより、デジタル化されていない情報も検索・分類・要約などの分析対象となり、議事録やホワイトボードの内容の活用、紙の記録の整理や共有に大きく役立ちます。そのため現場業務のデジタル化促進にも生成AIの活用は有効です。

文字起こしからの発言録作成
会議やインタビューの音声を生成AIツールで文字起こしし、発言者ごとに分けた発言録を自動で作成できます。
また話者の識別だけでなく、要点の抽出やキーワードのタグ付けも可能で、単なる会議の記録にとどまらず、会話の構造を視覚的に把握する手助けにもなります。
これらのAIツールを活用することで、議事録作成時間の大幅な削減はもちろん、内容の検索性・共有性の向上にも貢献します。
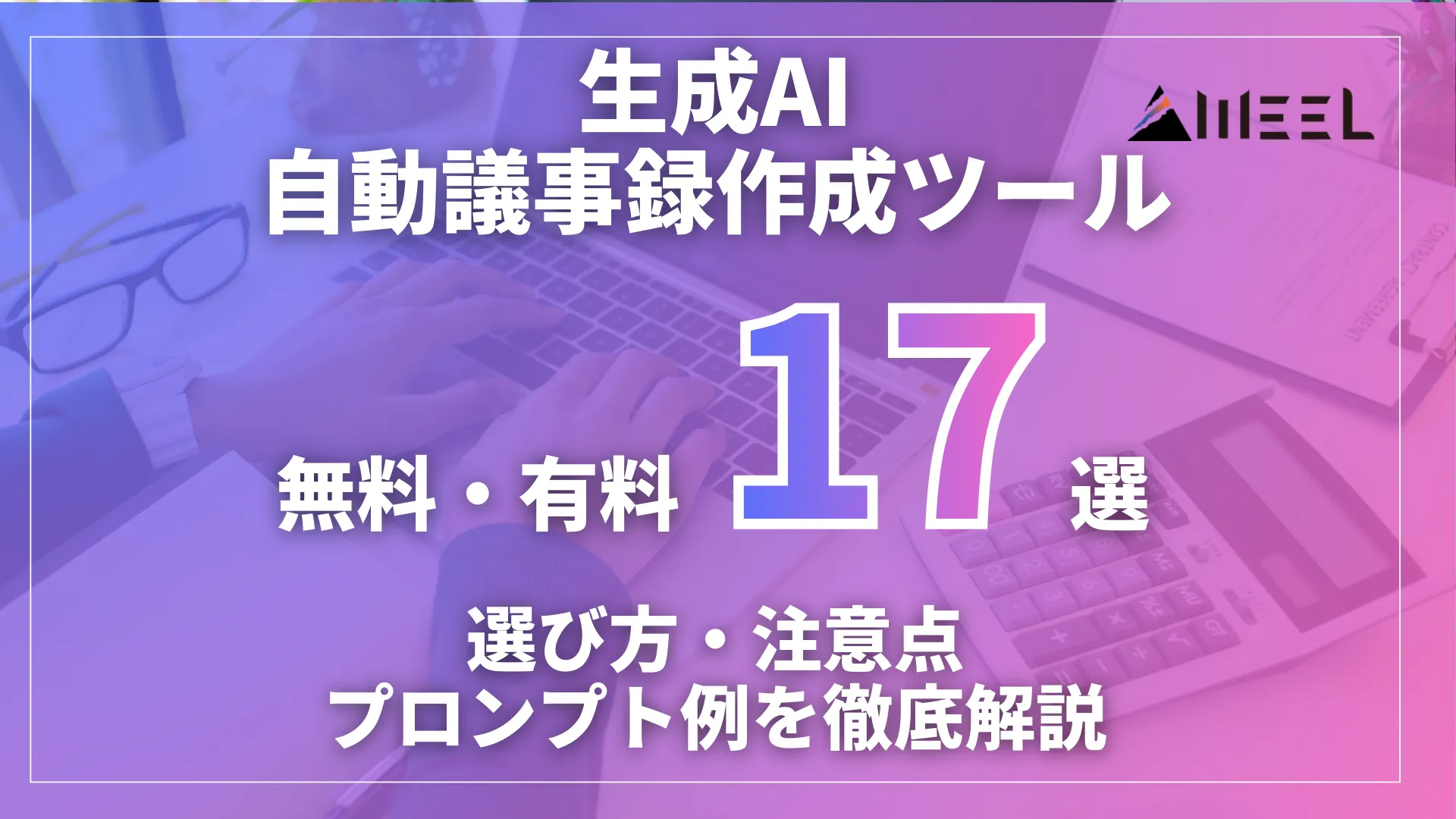
定性データの定量化・数値化
数値に表せない人間の感情や感覚などの定性的な情報は、これまで客観的な分析の素材としては不向きとされてきました。
しかし、アンケートの自由記述や各種のヒアリング記録など、回答者の主観的な定性データも生成AIで可視化・定量化することが可能です。
感情分析により、回答者の意見のポジティブ/ネガティブ分類ができるほか、キーワードの頻度集計で傾向の定量的な把握が可能。また、質的な情報を細かく数値化することで、より客観的な意思決定資料としても活用できます。

テキストマイニング
大量のテキストデータから特徴的な語句やテーマを抽出し、構造化することを「テキストマイニング」と呼びます。
生成AIは様々な文脈を理解しながら分析を行うため、関連性の高い情報同士をグルーピングしやすく、より精度の高いレポート作成が可能です。
このようなテキストマイニング機能を活用することで、SNSの投稿分析やレビューサイトの意見抽出など幅広く応用できます。
要約の作成
生成AIは長文の記事や専門的な学術論文、複数人が参加する会議の議事録など、大量の文字データを短時間で要約し、重要な情報のみを簡潔に整理することが得意です。
目的や読者に合わせて、箇条書きやストーリーの形式、要点整理など、要約のスタイルを柔軟に変えることも可能なため、情報共有やインプットの質向上に大いに役立ちます。
また、長編のYouTube動画の要約を作成すれば、視聴前に概要を確認できるほか、本当に自分が見るべき内容なのかを事前に確認することができ、無駄な時間を省くことが可能になります。
図表の作成
ChatGPTやGeminiなどの生成AIでは、自然言語のプロンプト(指示文)で構造や内容を指示することにより、表やフローチャートなどの図表を簡単に作成できます。
Markdownやプロンプトを上手に活用すれば、情報の比較や手順の視覚化が容易になり、資料作成にかかる手間を大幅に削減できます。
特に商談や会社のプレゼンテーションなど、視覚的に伝わるアウトプットが求められる場面で特に有効です。
リサーチ業務に使える生成AIツール

ここからはリサーチ業務に使える代表的な7つの生成AIツールについて、それぞれの特徴と主な料金プランを紹介します。
ぜひ、ご自身の業務に合うツールを見つけて、積極的に活用してみてください。その便利さにきっと驚くはずです!
ChatGPT
ChatGPTはチャット形式の対話型AIとして定評があり、情報収集や整理はもちろん、情報の要約やコード生成、画像や動画の生成などマルチに活躍します。また、カスタムGPTを使えば、特定の業務に特化したAIチャットボットの作成も可能です。
| 詳細 | |
|---|---|
| 主な機能 | ・OpenAI社が開発した対話型AIによる自然な入力が可能。 ・要約、資料作成、コード生成、カスタムGPTによる業務特化型チューニングやディープリサーチ機能も充実。 ・日常業務に役立つGPT-4o、GPT-4o miniをはじめ、高度な推論が得意なo3、o4mini、高度なEQを備えたGPT-4.5モデルを搭載。 ・通常のリサーチ業務はもちろん、ディープリサーチの活用により、より高度で広範な情報収集が可能に。 |
| 料金プラン | ・無料プラン:GPT4oが利用可能(一部機能に制限あり) ・ Plusプラン:月額$20(GPT-4.5にもアクセス可能) ・Proプラン:月額$200(高度な機能と優先アクセス) |
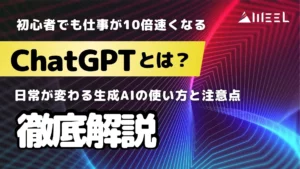
Gemini
Googleの親会社Alphabet傘下のGoogle DeepMindが開発した生成AIで、2023年12月に「Gemini 1」がリリース。マルチモーダル対応が特長で、テキストだけでなく画像・音声・コードの理解や生成も可能。
2025年3月には最新モデル「Gemini 2.5 Pro」も登場し、長文処理性能はもちろん、Gmail、DocsなどGoogleサービスとの連携が大幅に向上しました。
| 詳細 | |
|---|---|
| 主な機能 | ・Googleが提供するマルチモーダル生成AI。2025年5月に「Gemini 2.5 Pro Preview (I/O Edition)」も先行リリースされ、コード生成やマルチモーダル処理がさらに強化。 ・「Deep Research」機能は、複雑なトピックに対し、段階的な調査計画を立案し、数百のウェブサイトを自動で分析して、構造化されたレポートを生成。 ・高度な要約や自然な翻訳、効率的なコード補完に加え、Google Workspaceとの連携も強化。Gmailやドキュメントでの活用がよりスムーズに。 |
| 料金プラン | ・無料プラン:基本機能利用可能(Gemini Pro モデルに対応) ・Advancedプラン:月額$19.99(Gemini Ultra モデルに対応、2TBのクラウドストレージやGoogle Workspaceとの広範な連携機能を含む) |

Claude
Anthropic社が開発した生成AIで、元OpenAIの研究者らが中心となり設立されたスタートアップが提供するモデル。2023年に「Claude 1」、2024年に「Claude 3」シリーズが登場。人間に近い自然な対話と安全性重視の設計が特徴で、情報整理や文章生成、コード支援にも優れています。
| 詳細 | |
|---|---|
| 主な機能 | ・Constitutional AIという手法を採用し、倫理的なガイドラインに基づいた出力を行い、誤情報や有害コンテンツの生成を抑制。 ・最大20万トークンの長文コンテキスト処理能力を持ち、複雑な文書の分析や要約にも対応。 高精度な文章生成と要約はもちろん、コード生成やデータの可視化、テキストと画像の解析も可能。 ・長文要約や文章生成、コード生成やデバッグ、画像解析、ワークフローの自動化などに対応。Artifacts機能により、コードや文書、図表などの生成・管理が容易になり、業務効率が向上した。 |
| 料金プラン | ・無料プラン:基本機能利用可能(Claude 3.7 Sonnetモデルを利用可能) ・Proプラン:月額$20(3.7 Sonnetに加え、3 Opus、3.5 Haikuモデルも使用可能。無料プランの5倍のメッセージ利用や拡張思考モードの利用もできる) |
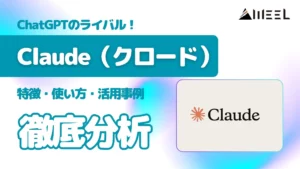
Perplexity
元GoogleやMeta、OpenAIなどで働いていた研究者たちが起業したアメリカのAIスタートアップ企業Perplexity AI社が開発し、2022年8月にリリースされた次世代型の検索エンジンAIツール。自然言語による質問に対して、信頼性の高い情報を引用付きで提供します。
| 詳細 | |
|---|---|
| 主な機能 | ・自然言語での質問に対し、関連性の高い情報を引用付きで提供するAI検索ツール。 ・GPTを活用した対話型のAI検索エンジンとSonarモデルにより、複雑なクエリにも対応可能。 ・「Pro Search」では、ユーザーの意図を深く理解し、詳細な回答を生成。また、ファイルのアップロードによる内容解析や、DALL-E 3、Stable Diffusion XLなどを用いた画像生成にも対応。 ・複数のAIモデル(GPT-4o、Claude 3.7 Sonnet、Gemini 2.0 Flashなど)を選択可能で、幅広い検索ニーズに対応可能。 |
| 料金プラン | ・無料プラン:基本機能利用可能(利用モデルの選択不可、PDFや画像のアップロードに制限あり) ・Proプラン:月額$20(高度な検索機能とAPIアクセスのほか、使用するAIモデルを選択可能。PDFや画像のアップロードも無制限に) |
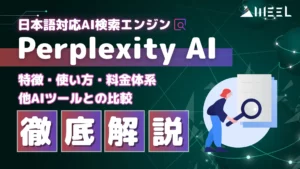
Genspark
Gensparkは、複数のAIエージェントが連携して情報を収集・分析し、ユーザーの質問に対して包括的な回答を提供する次世代型のAI検索エンジンです。従来のような、リンク一覧型の検索ではなく、多数のAIエージェントがWeb上を横断的に調査し、ソースと共に表示するため情報の信頼性も高いと評判です。
| 詳細 | |
|---|---|
| 主な機能 | ・ユーザーの検索クエリに対して、複数のAIエージェントが連携して情報を収集・分析し、リアルタイムで回答ページ(Sparkpage)を生成。 ・複数のAIエージェントが協力して情報を収集・分析し、信頼性の高い情報を統合して提示。 ・画像・動画生成やファクトチェック、スライド作成、通話代行など多機能を備えており、ビジネスや教育、研究など幅広い分野での活用が期待されている。 |
| 料金プラン | ・無料プラン:基本機能利用可能(一部機能に制限あり) ・Plusプラン:月額$24.99(すべての高度なエージェント機能を利用可能。新機能の先行利用もあり) |

Felo
Feloは東京を拠点とするSparticle社が、2024年7月にリリースした日本発のAI検索エンジンで、情報収集から整理、資料作成までを効率化する多機能ツールです。日本企業らしい細やかな工夫もあり、リリースからわずか1か月で全世界で15万人超のユーザーを獲得。現在も頻繁にユーザ目線でのアップデートが行われています。
| 詳細 | |
|---|---|
| 主な機能 | ・自然言語による検索に対応し、検索結果をもとにマインドマップやプレゼン資料(PPTX形式)を自動生成可能。 ・画像からの文字起こし・翻訳、音声メモの録音・文字起こし、AIエージェントによる市場調査など、多彩な機能を完備。 ・フォーカス機能により、学術論文やSNSなど特定の情報源に絞った検索が可能で、効率的な情報収集を実現。 |
| 料金プラン | ・無料プラン:通常検索は無制限、1日5回のプロフェッショナル検索も利用可能。 ・プロフェッショナルプラン:月額¥2,099(1日300回のプロフェッショナル検索、論文検索、マインドマップ生成、スライド生成など) |
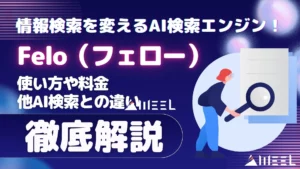
NotebookLM
NotebookLMは、Googleが開発したAI搭載のノートツールで、文書の要約、質問応答、音声解説など、情報整理と学習を支援する多機能なプラットフォームです。他のLLMモデルと異なり、ユーザー自身がアップロードした情報をソースに、AIが整理・分類・管理することで情報検索や学習を効率化します。
| 詳細 | |
|---|---|
| 主な機能 | ・GoogleのAIモデル「Gemini 2.5 Flash」を搭載し、複雑な推論や多段階の質問にも対応。 ・ユーザーは、アップロードした文書からAIによる要約や質問応答を受けることができ、情報の流出やハルシネーションのリスクが少ない。 ・PDFやGoogleドキュメント、ウェブページ、YouTube動画など多様な情報をソースとして取り込み可能。チャットの指示でソースから最適な情報を出力します。 ・音声解説機能「Audio Overview」により、76言語での音声要約が可能となり、音声学習や特定のトピックに関する音声配信素材の作成が可能に。 |
| 料金プラン | ・無料プラン:基本機能利用可能(Notebookの数やソース数、チャット回数に制限あり、オーディオ作成は1日3回まで) ・Plusプラン:Google One AI Premium(月額2,900円)に含まれる。チャットのみの共有も可能。 |

Notion AI
Notion AIは、Notionワークスペース内で利用できるAIアシスタント機能で、文章作成や要約、翻訳、タスク管理など、様々な業務効率化を支援します。GPT-4やClaudeの最新モデルを搭載し、SlackやGoogle Driveなどの外部情報にもアクセス可能。ビジネスマンやクリエイターに根強い人気です。
| 詳細 | |
|---|---|
| 主な機能 | ・GPT-4やClaudeなどの高度なAIモデルを活用し、ユーザーのワークスペース内の情報や接続アプリ(Slack、Googleドライブなど)から関連情報を取得し、パーソナライズされた回答を提供。 ・ダイアグラムやフローチャートの生成、PDFや画像の分析など、視覚的なコンテンツ作成にも対応。 ・文章の生成・要約・翻訳・校正、ブレインストーミング、タスク抽出、表やグラフの作成など、多彩な機能を提供。 ・テキストをハイライトしてAIに依頼することで、文法の修正やスタイルの調整も可能。AIブロックを挿入して要約やアクションアイテムの抽出を行うこともできる。 |
| 料金プラン | ・無料プラン:基本機能利用可能(回数制限あり) ・ AIアドオン:月額$10(年払いの場合は月額$8。Notion自体の有料プランの場合はAI利用は20%オフ) |
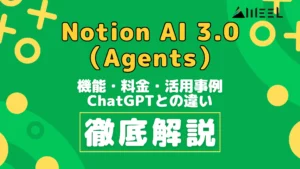
リサーチ業務における生成AIの注意点

生成AIは便利な一方で、使い方を誤ると誤った情報(ハルシネーション)による出力やそれに基づくリスクを生む可能性もあるため注意が必要です。以下にリサーチ業務における注意点と対応策について解説します。
ハルシネーション
生成AIは、一見それらしく見えるが実際は事実と異なる情報(ハルシネーション)を出力することがあります。AIのレベルが上がるほど、事実に交じって自然な流れでもっともらしい嘘をつく事があるため、必ずすべてを鵜呑みにせず、人間自身がソースとなる一次情報を確認して裏取りすることを習慣化しましょう。
情報漏えいのリスク
社内の機密文書や未公開情報をAIに入力する際は、情報漏えいのリスクに留意する必要があります。
まずはツールの利用前に、AI開発元の利用規約やデータ管理方針(入力データがAIの再学習に使われるか否かなど)を確認し、必要に応じて機密保持契約や社内ルールを整備することが重要です。
また、情報漏えいが心配な場合は、個人情報や機密事項を架空のものに書き換えるなど、ユーザー側の対策も必要です。
回答の偏り
生成AIは学習データに偏りがある場合もあるため、条件によって出力情報が特定の情報や視点に偏ることがあります。
そのため、生成された回答をそのまま鵜呑みにせず、複数の情報源と照らし合わせて検証する姿勢が求められます。
後述する検索特化型のAIツールには、参照した情報の出典元を複数示してくれる機能を標準搭載しているものもあるため、必要に応じて様々なツールを試しつつ、自身の用途に合ったリサーチ方法を見つける視点も大切です。
著作権侵害のリスク
AIが出力した文章や画像が、既存の著作物に類似するケースがあります。
特に商用利用を検討する場合は、開発元のポリシーの確認はもちろん、無用な著作権侵害のリスクを避けるため、出力データの内容確認とともに必要な権利処理(著作権者への許諾や出典の明記など)を怠らないことが重要です。
また必要に応じてAIやデジタルデータの権利関係に詳しい専門家の意見を参考にすると良いでしょう。
なお、ChetGPTの著作権問題について詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてお読みください。
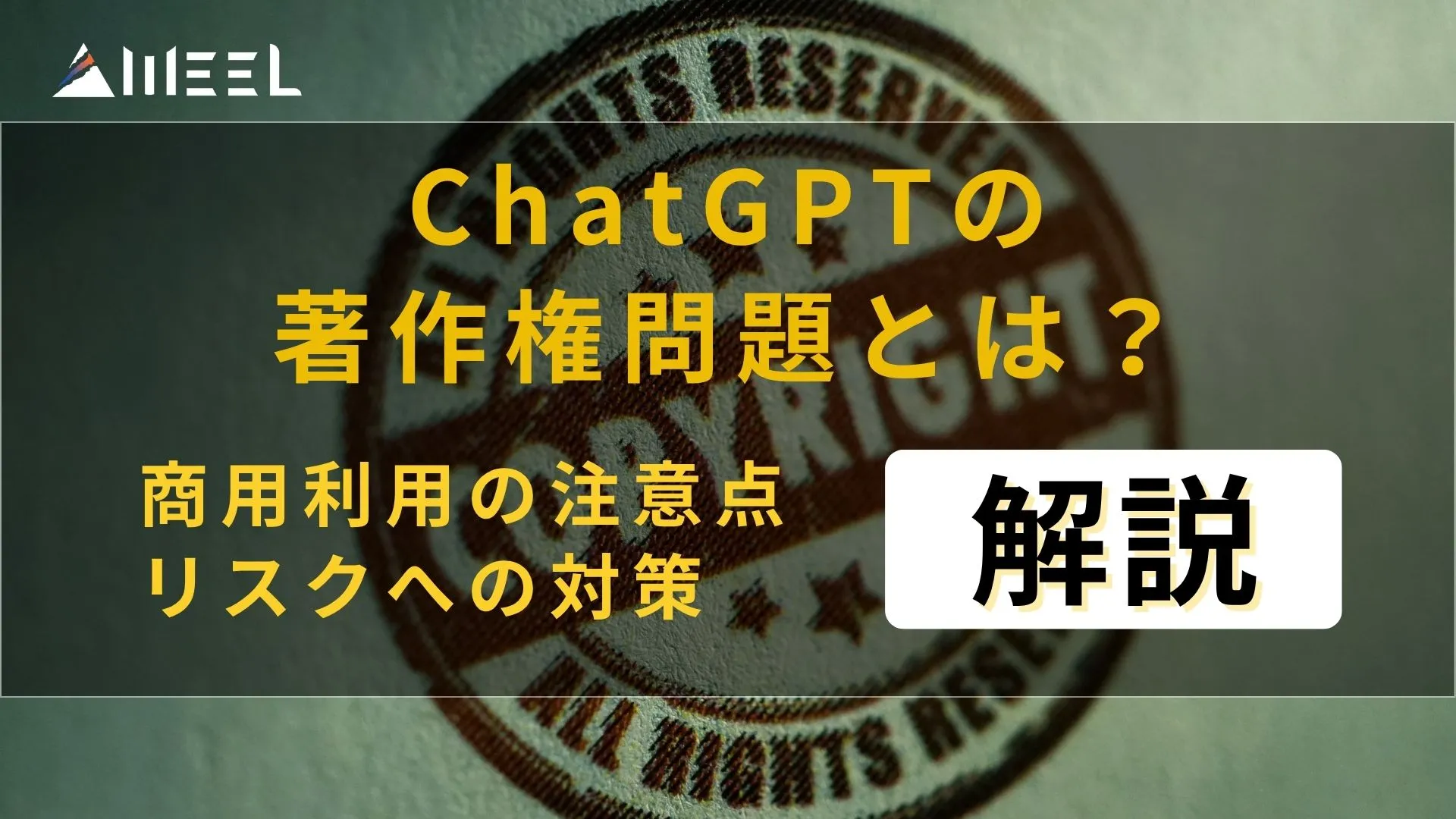
生成AIでリサーチ業務を革新する
これまでにご紹介した各種の生成AIツールを活用することで、リサーチ業務の効率化と質の大幅な向上が期待できます。またAIツールの利用には、以下のようなメリットがあります。
【生成AIによるリサーチ業務でできること】
- 情報収集の効率化: 大量の情報から必要なデータを迅速に抽出
- 多様なデータ形式への対応: テキスト、画像、音声、動画などを統合的に処理
- 要約と分析の自動化: 長文の要約やデータの分析を自動で実行
- 多言語対応: バイリンガル検索や翻訳機能で外国語圏の情報収集が可能
- コラボレーションの強化: 共有機能やマインドマップ生成でチーム内の情報共有が容易に
これらのツールを適切に組み合わせて活用することで、リサーチ業務の精度や生産性を大幅に向上させることができるでしょう。

最後に
いかがだったでしょうか?
自社の業務に生成AIをどう取り入れるべきか。リサーチの質とスピードをどう両立するか。事例をもとに、目的に沿ったツールの選定や導入プロセスを整理したい方に向けて、具体的な活用像と成果につながる設計方法をご紹介します。
株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!
開発実績として、
・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント
・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット
・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト
・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール
・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用
・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント
などの開発実績がございます。
生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。
➡︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。
まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。
➡︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。
セミナー内容や料金については、ご相談ください。
また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。

【監修者】田村 洋樹
株式会社WEELの代表取締役として、AI導入支援や生成AIを活用した業務改革を中心に、アドバイザリー・プロジェクトマネジメント・講演活動など多面的な立場で企業を支援している。
これまでに累計25社以上のAIアドバイザリーを担当し、企業向けセミナーや大学講義を通じて、のべ10,000人を超える受講者に対して実践的な知見を提供。上場企業や国立大学などでの登壇実績も多く、日本HP主催「HP Future Ready AI Conference 2024」や、インテル主催「Intel Connection Japan 2024」など、業界を代表するカンファレンスにも登壇している。